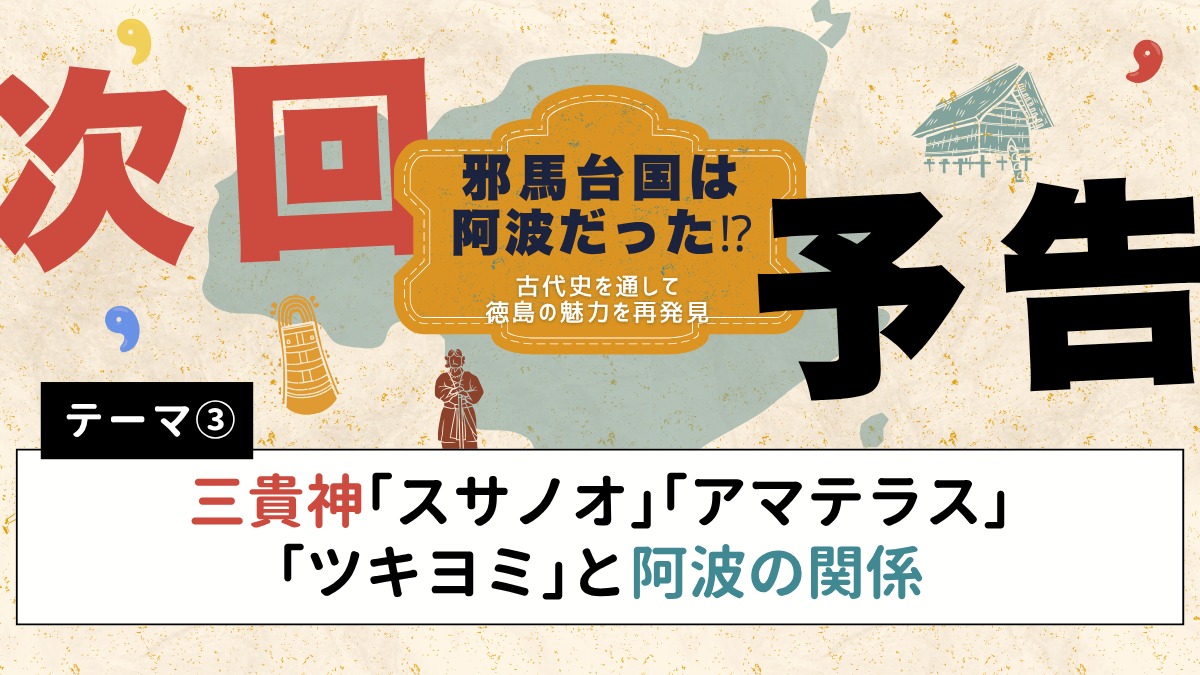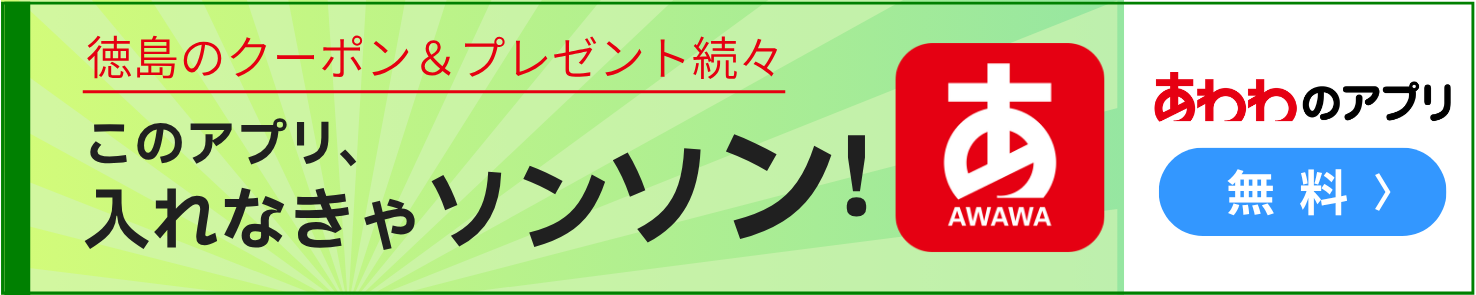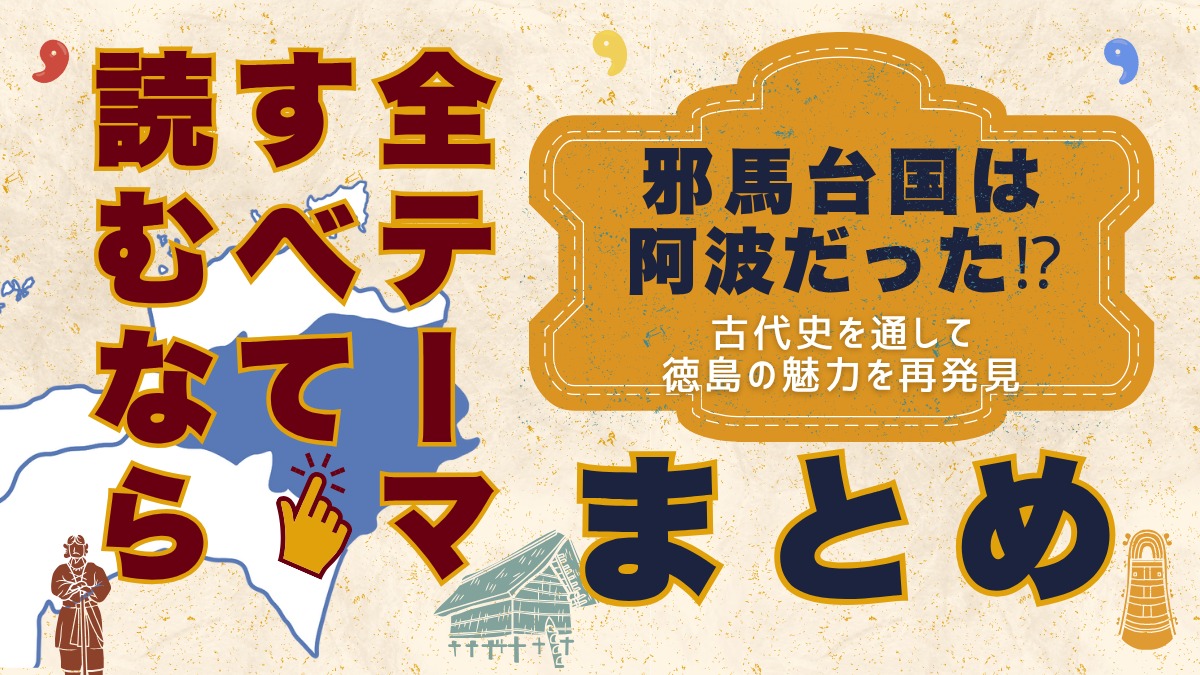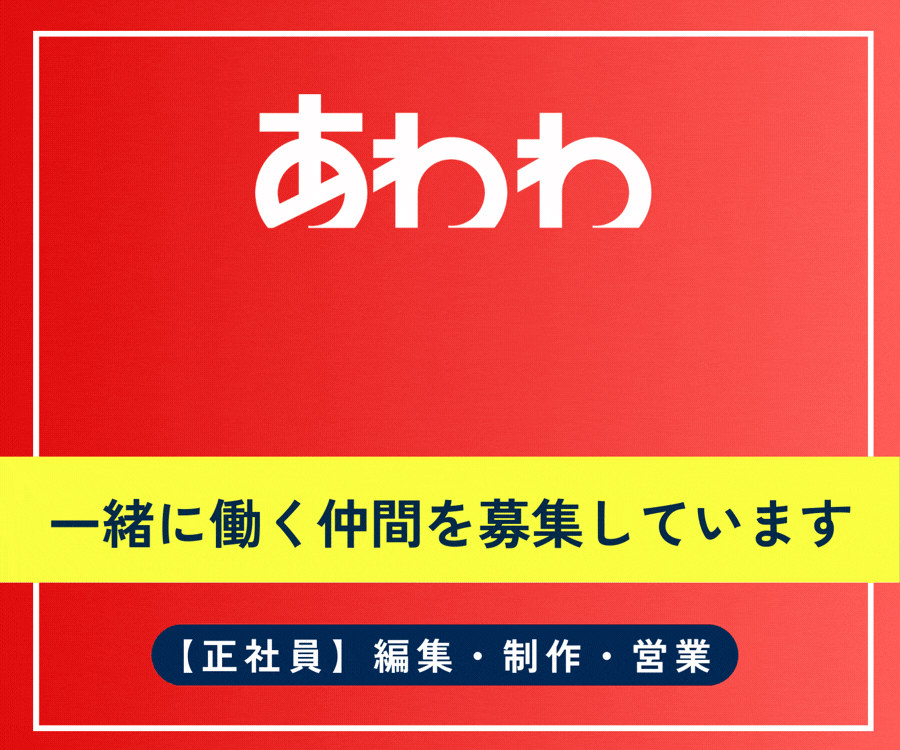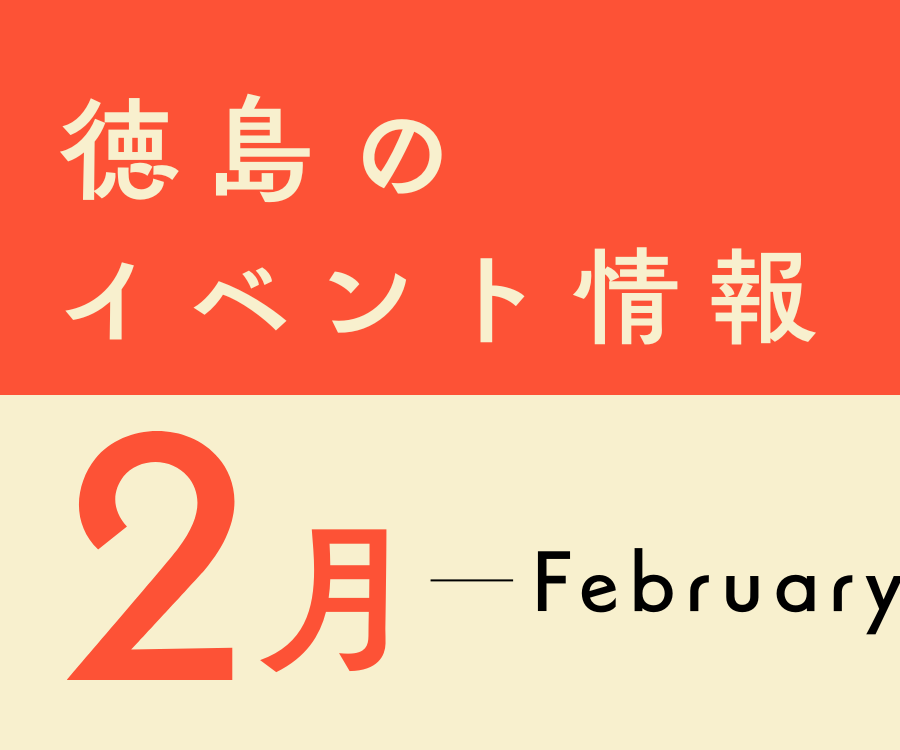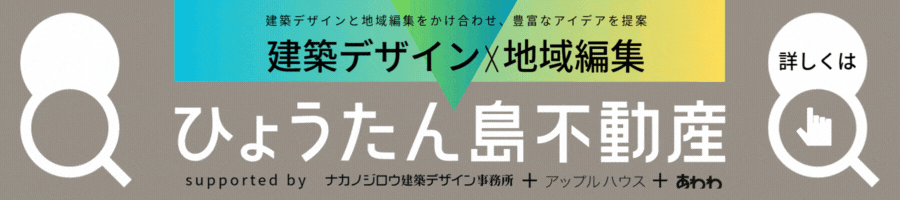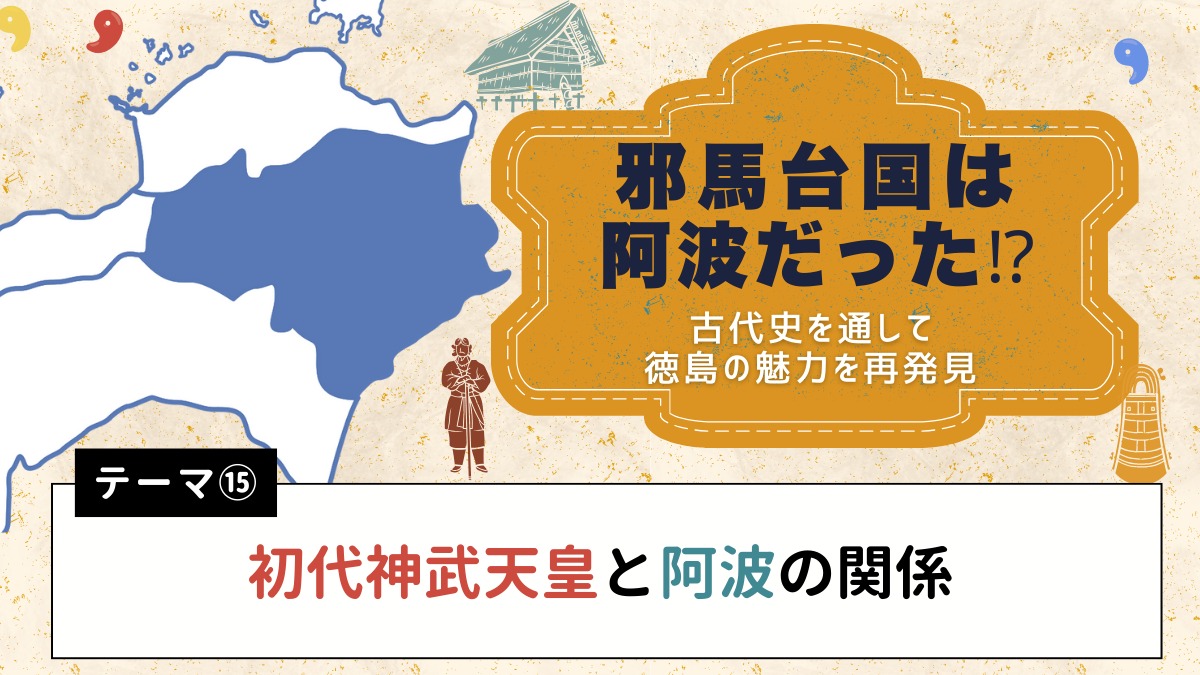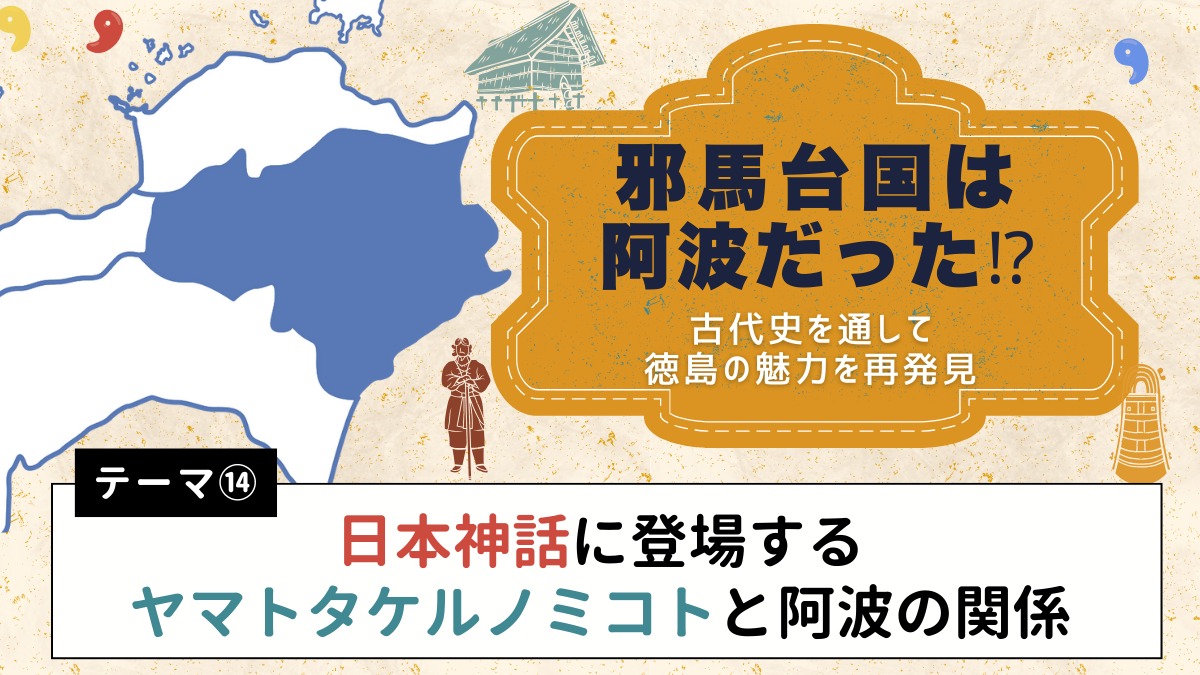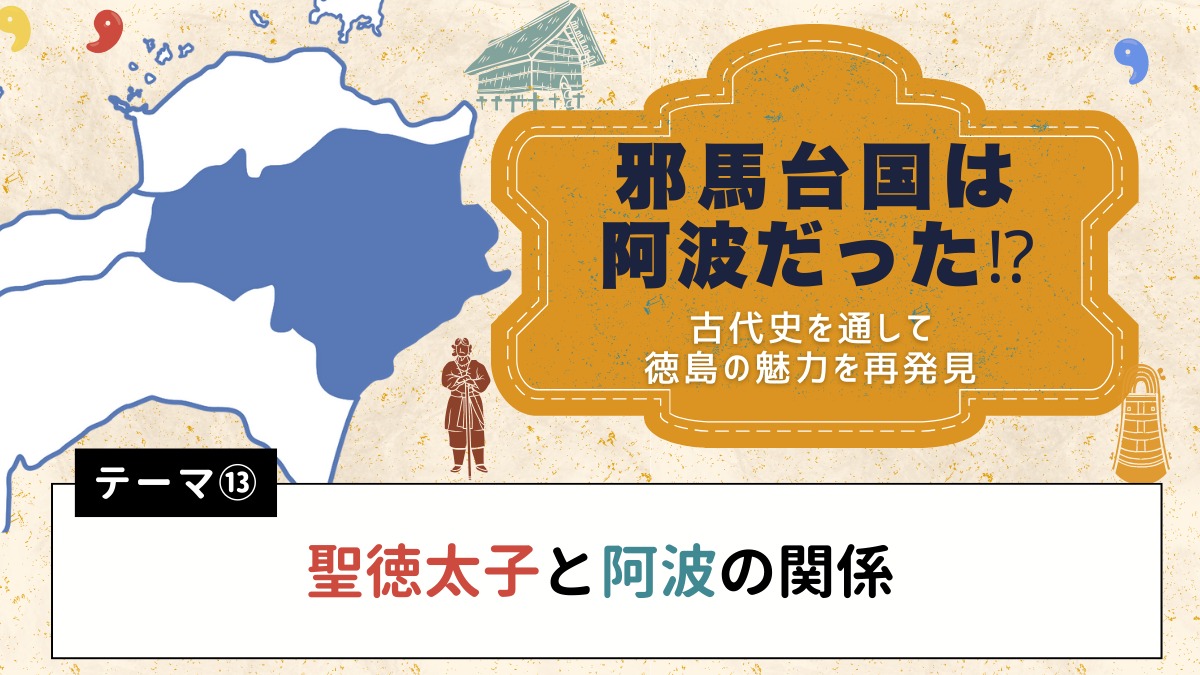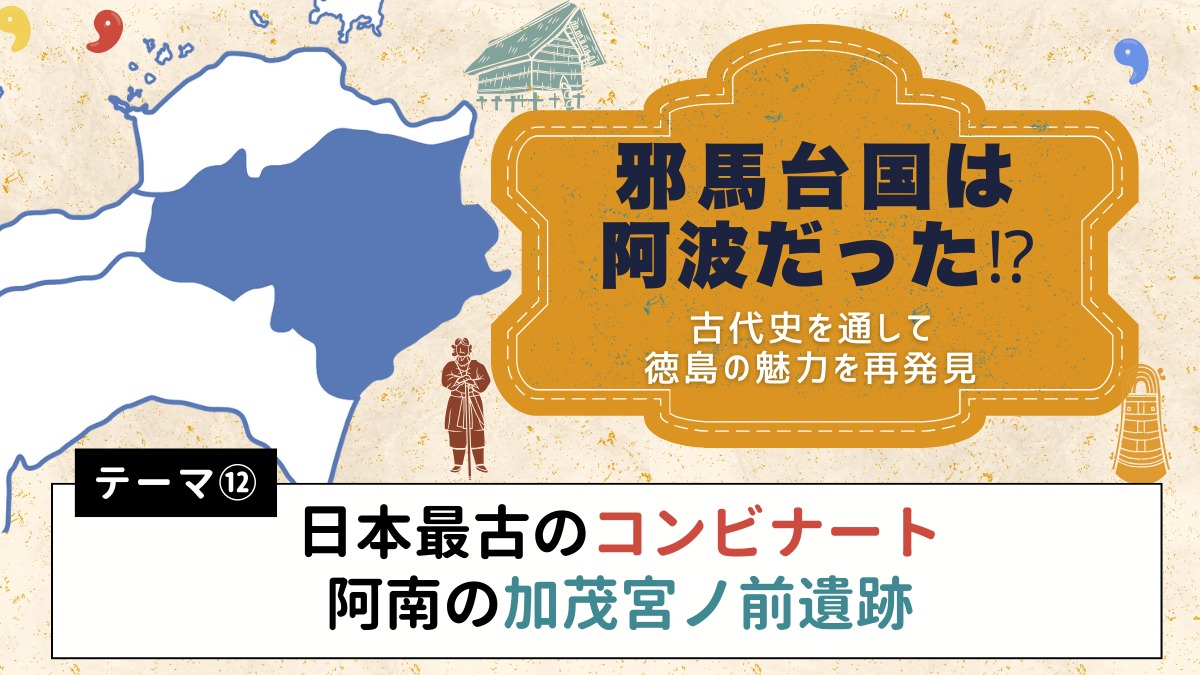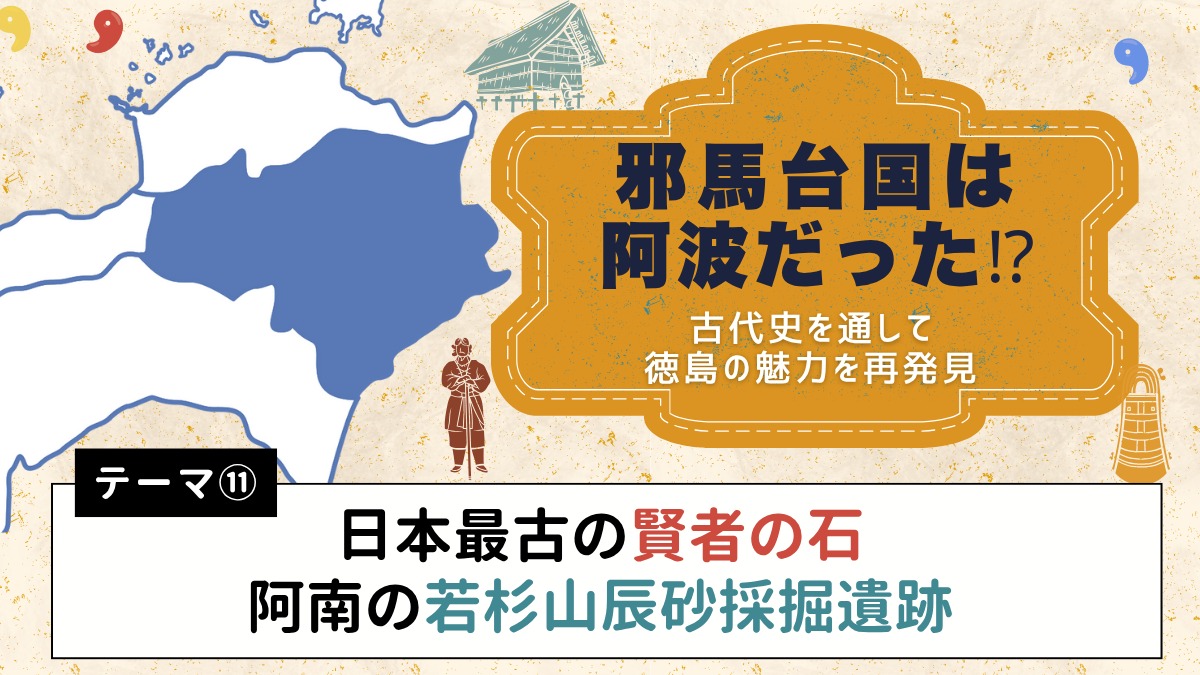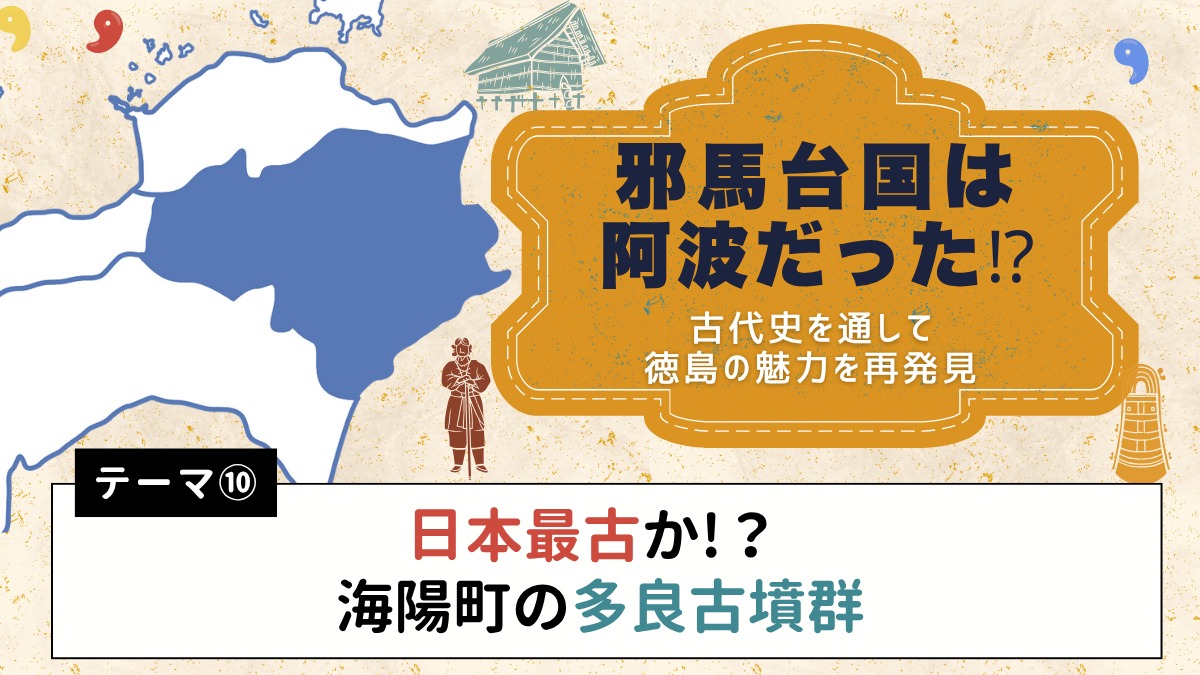2025/07/15 01:00
あわわ編集部
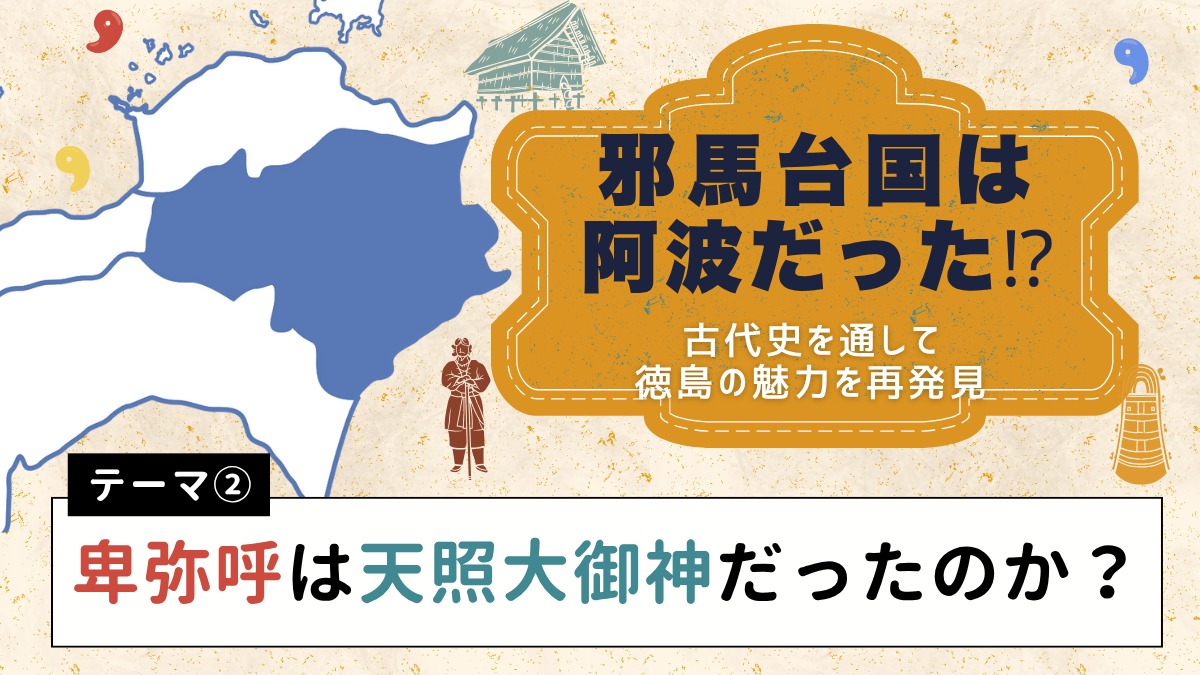
邪馬台国は阿波だった!?【古代史を通して徳島の魅力を再発見】テーマ②卑弥呼は天照大御神だったのか?
小学生の社会の授業で習う、あの「邪馬台国」が阿波徳島にあったかもしれない説が盛り上がっている。魏志倭人伝など各歴史書からも符号する事象が多くあり、邪馬台国阿波説に関する書籍やWEB記事、YouTubeなどで各執筆者が自分の説を論じている。ただ、阿波説は完全一致していなくて(そこがまた歴史ロマンにあふれている!)、それぞれ積み上げてきた研究で自身の説を発信しているのが現状。1800年も前の出来事を完全一致させることはほぼ不可能ということで・・・。それならば!それぞれの論者の説を一同に掲載することで、各説の微妙な違いや逆に一致している点などを比較できるようにしようと、まとめ記事を企画しました。この無謀かつ挑戦的な企画にもかかわらず、快諾していただいた執筆者はなんと8名も!毎回のテーマごとにエントリーして執筆してもらうスタイルでまとめていきます(エントリーしないテーマのときもあります)。それぞれが論じる内容を読み比べ、納得する説をお好みでチョイスしていってください。なお、当企画は阿波の古代史を通して徳島の魅力を再発見するというのがミッションなので、邪馬台国以外のテーマも登場予定です。
※注※
この連載コーナーは、各執筆者の考え・主張をまとめたもので、あわわWEB編集部として特定の説を支持する立場でないことをご理解ください。内容に関する問い合わせなどにつきましては、各執筆者に直接連絡してください。
また、本記事の内容は著作権法により保護されています。無断での転載、複製、改変、及び二次利用は固く禁じております。記事自体のシェアは大歓迎です。
邪馬台国は阿波だった!? テーマ②/「卑弥呼は天照大御神だったのか?」
通説
卑弥呼はだれなのか! 【①神功皇后説】神功皇后は他の古代の女帝と比べても格段にシャーマン的要素の強い女帝であり、神の名のおくり名を持つ。神功皇后は、「巫女王」という卑弥呼の情報には合致する人物だが、「夫なし」とされた卑弥呼に対して神功皇后はその名の通り仲哀天皇の后であるなど矛盾もある。【②アマテラス説】卑弥呼=アマテラス説は戦前の学者によって主張された。卑弥呼もアマテラスも男弟(スサノオ)が重要な役割を演じている事など類似点が多い事や卑弥呼の死の前後に起こったとされる日食と天の岩戸神話の関連性や延喜式内社等の系図に着目した議論も進んでいる。【③ヤマトトトヒモモソヒメ説】7代孝霊天皇の皇女・ヤマトトトヒモモソヒメ(倭迹迹日百襲姫)を卑弥呼とするのは、彼女の生きた時代を3世紀中頃(邪馬台国全盛期)とみる事で数世代後の神功皇后よりも年代論的に説得力があり、三輪山の大物主神の妻になったという伝説を持つ女性で、神に仕え人間の夫を持たなかったという意味でも、卑弥呼に重なってみえる。ただ通説では、彼女の父であった孝霊天皇は「欠史八代」の1人であり、現在では存在しなかった人物であったと考えられており、疑問も残る。【④「卑弥呼職業」説】「卑弥呼=邪馬台国女王」と言われているが、「卑弥呼」は固有名詞ではなく、倭国大乱を収める為に生み出された役職だったという。卑弥呼は女王ではなく、邪馬台国連合を治める倭国王の正統性を保証する「卑弥呼職」という職業だったとする説だ。
島勝伸一氏の説/女王卑弥呼は天照大神さまか?を特定する
同じく、日本の歴史書は残っておらず、漢字が入る前、すでに日本には神代文字が存在していたことは、聖徳太子の17条の憲法や天武天皇の歴史書編纂の詔の中に旧辞や帝紀があったことが分かる(これらをすべて闇に葬った権力者がいたと思う)。魏志倭人伝によると220年頃邪馬壹国(やまと)の女王卑弥呼を共立した女王国があり、239年には女王国卑弥呼から魏の明帝に朝貢し親魏倭王の称号と金印を受けるときされている。
また卑弥呼が没した248年後男子の国王が就任したが、国が乱れ、253年卑弥呼の宗女13才の壹與が女王になり治まった。この頃、卑弥呼の墓は矢野の神山に築かれた宮谷古墳が卑弥呼=大日霊女命=天照大神だと思われる。天岩石別八倉比賣神社の創建は、仏教の伝来で社殿・神殿を作るようになった6世紀以降と思われる。そのほか、日本史年代には、西暦年との整合性がなく、皇紀のごとくは、まったく世界史年表と合わない。この問題解決は以下のとおりです。
日本史西暦年表示220年卑弥呼女王国の女王に共立さる、住まいは邪馬壹国239年魏の明帝に朝貢し、親魏倭王の称号と金印を受ける。248年卑弥呼没。男子の国王が就任したが、国が乱れる。253年卑弥呼の宗女13才の壹與が女王となり治まった。この後、西暦で年代が確定するのは593年33代推古天皇即位迄約340年の空白がある。そこで、248年卑弥呼(天照大神=皇祖)没から5代後が初代神武天皇であるなら、そこから592年まで32代の年月と推古天皇即位から32代後65代花山天皇没(986年)までの年数比較により、神武天皇即位の年はおおよそ見当が付く。
もう一つ神武天皇即位に関し、辛酉の年との表記があるので西暦301年となると、一代の在位年は9.125年となる。次の33代から65代までは12.281年となります。さらに次の66代から88代までの32代は12.406年となり、天皇在位が100年超が8人もあるような日本史年代のウソが分かる。以上のように魏志倭人伝によって、日本史が具体的に読み取れるようになりました。また次号でお会いしましょう。

【執筆/島勝伸一(しまかつしんいち)】 [問い合わせ先]080-3533-5146(島勝) |
島勝伸一氏の説をもっと詳しく知りたい方は・・・
▶▶島勝伸一解説 岡元雄作監督作品 ドキュメント映画『ルーツ オブ ザ エンペラー』令和6年6月27日 四国古代史サミット東京(YouTube)
藤井榮氏の説/卑弥呼は「日孁命(ひるめのみこと)」(実在神)で天照大御神(あまてらすおおみかみ)は後世の“創作神名”
皆さんもよくご存じのように「卑弥呼」は中国の歴史書(魏志倭人伝)に出てくる邪馬臺国(やまとこく)の女王の名で、「天照大御神」は「古事記」(天皇を中心とする国家統一の思想で貫かれた天皇家の歴史書)に出てくる皇祖神(こうそしん)(天皇一家の先祖の神)の名ですよね。この「卑弥呼」と「天照大御神」が同一人物なのかどうかということについては、「卑弥呼」が日本歴史上の誰なのかということを含め学者・アマチュア研究者の間でいろいろな見解が示されております。私は一介の古代史学徒ですが、阿波の大先覚岩利大閑の著『道は阿波より始まる』(一~三)に学んだことを踏まえてお話をさせていただきます。
邪馬臺国が阿波であることは前回のテーマでお話しましたが、「卑弥呼」は中国から見た呼び名(漢字)で阿波では「日の皇子命(ひのみこのみこと)」・「日神子命(ひみこのみこと)」と呼ばれており、その名残が徳島市南部の大原町(紀伊水道に面した“大神子海岸”)に今も残る「大神子(おおみこ)」・「小神子(こみこ)」という地名です。 私は「卑弥呼」(日神子)は古事記に記された「天照大御神」のことであると考えていますが、実は阿波ではこの「天照大御神」の神名は一切出て来ないのです。延喜式内社(えんぎしきないしゃ)[※]の古社をはじめ山分(さんぶん)(神山町・佐那河内村などの山間部)その他の古社の神名帳(じんみょうちょう)にも「天照大御神」という神名は見当たりません。
大閑氏によれば阿波国風土記と天石門別八倉比売(あまのいわとわけやぐらひめ)大神御本記(由緒書き)は全く同一の内容ですが、「天照大御神」という神名はこの両書にも現れません。なので、「天照大御神」という神名は古事記撰定時かその後に新たに作り出された名で、したがって「天照大御神」という神名を祭神とする神社も「古事記」撰定後に作られた新しい神社であると考えられます。 阿波では古来「天照大御神」のことを「大日孁命(おおひるめのみこと)」と呼んでいますが、これは前述の「日神子命」の死後の諡名(おくりな)(しごう)なのです。徳島市国府町西矢野に鎮座する天石門別八倉比売神社のご祭神こそ「大日孁命」、即ち「日神子命」、魏志倭人伝の「卑弥呼」です。
以上のことは、万葉集巻二167番の歌を見ればよく分かります。 『日並皇子尊(ひなみしのみこのみこと)の殯宮(あらきのみや)の時に柿本人麻呂の作れる歌一首併せて短歌 天地(あめつち)の 初(はじめ)の時 ひさかたの 天の河原に 八百万(やほよろず) 千万神(ちよろづがみ)の 神集(かむつど)ひ 天照らす 日孁命(一は云はく、さしのぼる日女命(ひのめがみ)) ‥‥高照らす 日の皇子(ひのみこ)は ‥‥天皇(すめろぎ)の 敷きます国と 天の原 石門(いはと)を開き 神あがり あがり座(いま)しぬ ‥‥(以下略) 』 。(中西進 訳校注「万葉集(一)」講談社文庫)
[※]律令の施行細目を収めたもの(格式)が「延喜式」で、927年に撰上(せんじょう)され、その巻九・十には朝廷が幣帛(へいはく)(ぬさ:神に奉る物の総称)を供える重要な神社として全国で3,132座が登載されており、これを「延喜式内社」といい、これが登載されている九・十のことを「延喜式神名帳」といいます。

▲徳島市にある天石門別八倉比売神社、奥の院の卑弥呼神陵。

【執筆/藤井榮(ふじいさかえ)】 [問い合わせ先]sakae-f-1949@ma.pikara.ne.jp |
藤井榮氏の説をもっと詳しく知りたい方は・・・
▶▶古代史塾(公式HP)
▶▶古代史塾(YouTube)
オキタリュウイチ氏の説/ ― 徳島側から見ればわかることもある ―
「伊勢神宮」。三重県にある、日本で最も重要な神社の一つ。日本人なら、その存在を知らない人は居ないと思います。しかし、公式ホームページにも「ご鎮座の歴史」の記録があり、「元伊勢」として、奈良、滋賀、岐阜など、160回くらい引っ越しを繰り返しています。「最後に辿り着いたのが、伊勢」という訳です。では、最初はどこからスタートしたのでしょうか?
阿波・徳島には、「卑弥呼の古墳」があります。気延山に鎮座する「天石門別八倉比売(あまのいわとわけやくらひめ)神社」です。そこに祀られている神の名は「大日孁(おおひるめ)」 で、阿波では、天照大御神を大日孁と呼びます。本殿奥之院には古墳があり、神社に残っている古文書「御鎮座本記」には、天照大御神の「葬儀の様子」が記されているのです。また皇室との深い関係も残っています。大東亜戦争終戦以前までは、天皇の勅使が毎年、直接天石戸別八倉比売神社に参じていました。天皇勅使から直接幣帛(へいはく)を賜っていたのです。
私は、このように考えています。実在の人物をモデルにしたようなドラマでは、わざと実在の名前と役名を変えることがあります。「卑弥呼が、歴史ドラマでは天照大御神と呼ばれている」と考えるのが自然ではないでしょうか? また、神社がある気延山(きのべやま)も超重要です。天照大神が、高天原から孫の瓊瓊杵尊(ニニギノミコト)を地上に送る前に、2人の神を地上に派遣します。「天忍日命(あめのおしひのみこと)」「天津久米命(あまつくめのみこと)」 という神です。忍日命の子孫は、大伴さんになり、後に田村さんになります。そして、久米命の子孫は「久米さん」の姓になりました。 この久米姓と田村姓。気延山周辺に極端に多いのです。昭和55年に久米さんの子孫が行った調査では、徳島県に久米姓の42%(540戸)が集中していました。久米さんは戦前、「宮崎の高千穂にニニギノミコトが天孫降臨した」と教科書で読み、「さぞ、久米さんがいっぱいいるんだろうな!」とワクワクしたそうです。そこで、高千穂に久米さんがいるか調べたら、なんとゼロだった!宮崎全域でも、たったの19戸しか無かった事に愕然とします。
じゃあ、天孫降臨の地はどこだったのでしょうか。頭のいい読者の皆さんは、もうお分かりですね。 徳島は銅鐸の出土数が日本で最多です。気延山付近から出土した銅鐸も、国内最大級なのです。銅鐸は、稲霊(いなだま)を呼び、豊穣を願うための祭具です。日本最大級の銅鐸が出土しているということは、この地こそが、太古の祭祀の中心だったという事でしょう。気延山自体にも、1000基を超える古墳が発見されています。夫の不在。弟の存在。皆既日食。内乱と平定。卑弥呼と天照大神には、構造的に一致している箇所が驚くほどあります。 天照大御神は、日本最初の「引きこもり」経験者です。だからこそ、強くなれた。そして、最初の神ではないのに、「最高神」となります。ここにこそ、日本の美しさがある。 元伊勢のスタート、気延山。 こんなに近くに、偉大な聖地があったのです。
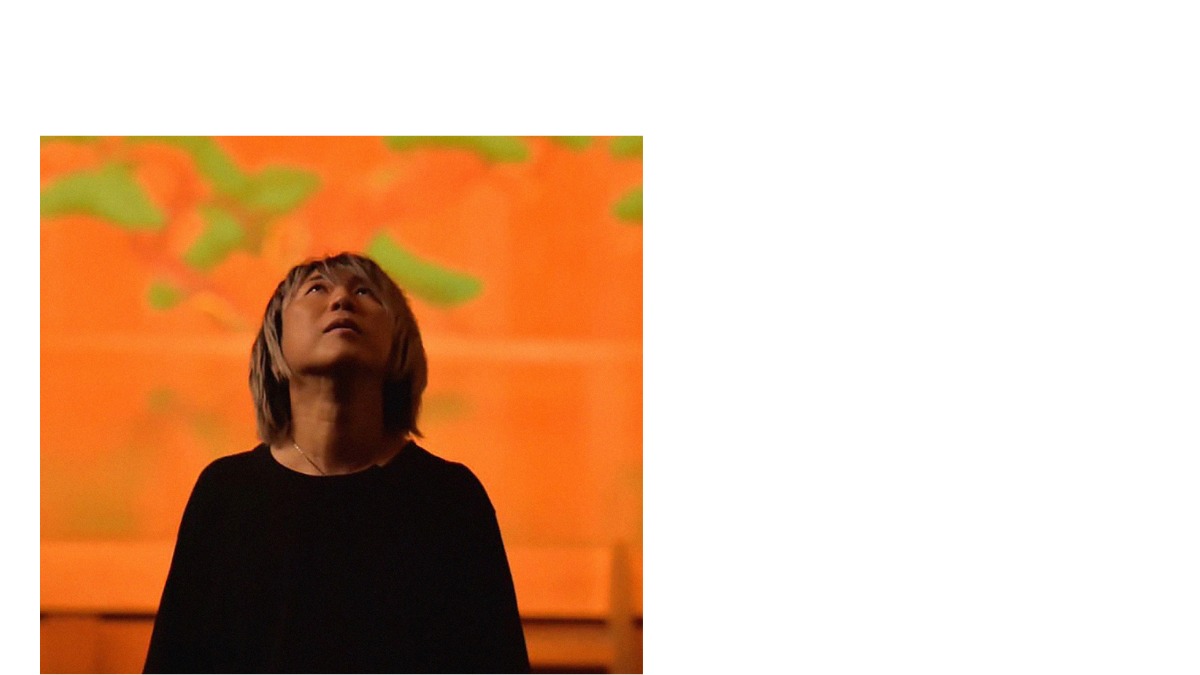
【執筆/オキタリュウイチ】 [問い合わせ先]office@deepbranding.jp |
オキタリュウイチ氏の説をもっと詳しく知りたい方は・・・
▶▶公式ホームページ
恋塚建生氏の説/卑弥呼は天照大御神であるが、○○も天照大御神である
私は天皇在位10年説を支持しています。この説は、天智天皇以前の天皇の在位が、10年平均であるとの研究内容からくるものです。天智天皇が死去した年(西暦672年)-天智天皇が38代天皇であること。すなわち(672-10☓38)≒西暦300年前後が、神武天皇が生きておられた年代ではないかと予想されます。一般的な古事記の系図がアマテラス→オシホミミ→ニニギ→ヤマサチ→ウガヤフキアエズ→神武天皇となるので、西暦300年-50年≒西暦250年となり、魏志倭人伝における卑弥呼が死去した年(西暦247年?248年?)とほとんど重なり、卑弥呼が天照大御神であると推測されます。
しかし、古事記を読み解くと、矛盾点もあり絶対にそうであるとも言えません。それが古事記神話(阿波古事記神話)が伝える深い所です。それは後のテーマである、「日本神話に登場する天岩屋戸と阿波の関係」で、詳しく説明したいと考えます。ただ今言えることは、阿波には古事記神話に関係する祭り事が現在も残っていますが、現在の阿波の人がなぜそんなことをしているのか?わかっていないということです。
最後に、プロフィールの欄や前回のテーマに書いているように、魏志倭人伝の読み解きには数学の知識、ITそれと極東の地図が必要でした。古事記の読み解きには何が必要か?それは漢字の知識、IT、それと徳島県の地図です。もっと掘り下げて言うと阿波・徳島の地形、地名、川、海、山などの固有名詞の知識がなければ、古事記は読み解けません。すなわち、徳島県民でなければ、古事記の読み解きは困難で、知識者や国学者研究でも答えが出ない理由がまさしくそこにあります。
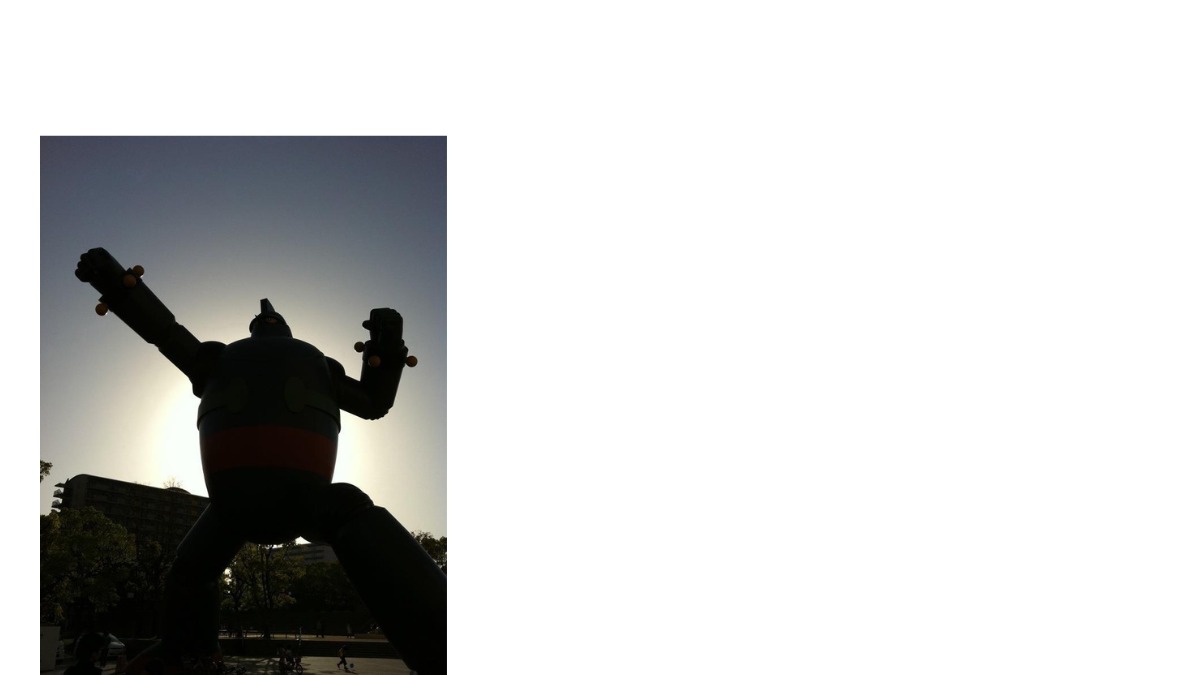
【執筆/恋塚建生(こいづかたけう)】 [問い合わせ先]ogenkisama0@gmail.com |
恋塚建生氏の説をもっと詳しく知りたい方は・・・
▶▶魏志倭人伝を最新技術で読み解いた!(YouTube)
ANYA氏の説/日本の歴史書に卑弥呼の名が登場しないのは、、当然です
中国の歴史正史、魏志倭人伝に、日本の最初の女王として記された卑弥呼が亡くなったのが248年、一方日本の歴史正史である日本書紀には、248年は14代仲哀天皇の御代となっています。つまり魏志倭人伝・日本書紀の両正史が正しいとすれば、仲哀天皇の時代に女王卑弥呼が存在していたと言う事になります。仲哀天皇の后は、日本最初の紙幣の肖像画にもなった、有名な神功皇后です。神功皇后は大正15年に歴代天皇から外されましたが、それまでは日本初の女性天皇(15代)とされ、大正時代までは紙幣にも描かれるなど、誰もが知る最も有名な歴史上の人物の一人でした。卑弥呼の時代と時を同じくしている事から、神功皇后こそが卑弥呼であると日本書紀編纂時から、殆んどの人がそう考えていたと思われます。
しかし世が進むにつれ、神功皇后がたとえ実在したとしても、卑弥呼の時代の100年近く後の時代という事がほぼ間違いないと考えられ、これは記紀編纂者が意図的に神功皇后を卑弥呼にあてがったとも思われます。また、初代から21代位の天皇の年齢は、日本書紀によると143才など、常識では在り得ない年齢になっています。これは、古代日本は年齢を年2才重ねる、春秋2倍歴という数え方をしたと考えられ、仮に21代までの年齢を2で割ると、おおよそ900年も過去に遡っている事となります。初代神武天皇の即位が紀元前660年、これを900年元に戻すと、神武天皇即位は紀元前660年ではなく、西暦300年位の出来事という事になります。
神武天皇は、天照大御神の5代孫にあたり、20才で子供を産んだと考えると、20才☓5代で100年、という事は神武天皇即位の100年前、西暦200年位に天照大御神が存在していた事になります。卑弥呼が亡くなったのが248年、仮に50才位で卑弥呼が没したとなれば、生まれたのは西暦200年位、つまり、卑弥呼と天照大御神は、日本の同じ時代にトップに君臨した女性という事から、同一人物と考えるのが、いちばん自然ではないでしょうか。ではなぜ、卑弥呼が天照大御神と同一人物とはされていないのか? それは、卑弥呼が中国皇帝に頭を下げ朝貢していた事実が有るために、もし同一人物だった場合、皇祖神天照大御神がそれを行ったことになってしまうからではないでしょうか
*公式YouTubeチャンネルの㉕『阿波から日本が始まった、拡散用』を参照。

【執筆/ANYA(アンヤ)】 [問い合わせ先]anyautb@gmail.com |
ANYA氏の説をもっと詳しく知りたい方は・・・
▶▶ANYAチャンネル(YouTube)
コラク氏の説/阿波に息づくアマテラスとヒミコのパラフレーズ
日本最古の歴史書「古事記」に記される八百万の神々の頂点に立つ最高神であり、現在の皇祖神と伝わるアマテラス。一方、3世紀末の中国の歴史書「魏志倭人伝」に登場し、親魏倭王の金印を拝受したとある邪馬台国の女王卑弥呼。 果たしてこの二人の女性が同一人物であったのか。
古事記によると、スサノオが高天原を追放された後に食物神である大宜都比売と邂逅する場面がある。この神は阿波国の別名と明記されており、神山町の上一宮大粟神社にて祭祀されている事からも、古事記の舞台が阿波であった可能性を仄めかす。また近隣にある天石門別八倉比売神社(国府町)には、スサノオの姉のアマテラスが御神陵(前方後円墳)を含む杉尾山自体をご神体としてご鎮座する。社伝の御本記にはアマテラスの葬儀のご様子が記されており、その解説本となる「杉の小山の記」(1831年)には、「大神は前に天より持ってきた瑞の赤珠(みつのあかたま)の印璽を、杉の小山の嶺に深く埋めて、天の赭(あかつち)で覆い納めた。赭の印璽と言って秘し崇め奉ったのはこれである。その印璽を埋めた所を印璽の嶺という。」とある。この神陵を中心とする気延山古墳群は、約200基からなる未調査の古墳が今も眠っており、倭人伝に「卑彌呼以死大作冢 徑百餘歩 狥葬者奴碑百餘人」「卑弥呼の死によって大いに塚が作られた 径は百余歩 殉死した奴婢は百余人」とある事からもこれらがその塚跡の可能性もある。
また異称である大日靈女命(おおひるめ)の神名を註解すると、「靈」の俗字「巫」の読みは「み」であり、後字の「女」と合わせ読むと「巫女(みこ)」、従って大は美称+日+靈女(ひ・みこ)となる。また考古的視点からは、2世紀末~3世紀初頭の築造で前方後円墳の祖型とされる鳴門市の萩原2号墓は、奈良県で最古級の古墳とされるホケノ山古墳のルーツとみなされている事からも、これらが阿波から進出した証拠とする考えを裏付ける要因にもなる。
こうした痕跡は鮎喰川流域を中心とした吉野川河口域の歴史事例の記録であった可能性があり、墳型は後のヤマト王権の象徴的特徴を有する事からも必然的に阿波と奈良の関連性にプライオリティを置く必要があるだろう。纏めると、アマテラスと大宜都比売のどちらが卑弥呼だったのかを検証する必要があるが、これらが異名同神の可能性も否定できない。ただし現時点で結論を出すならば、アマテラスが卑弥呼であった公算が高いといえる。
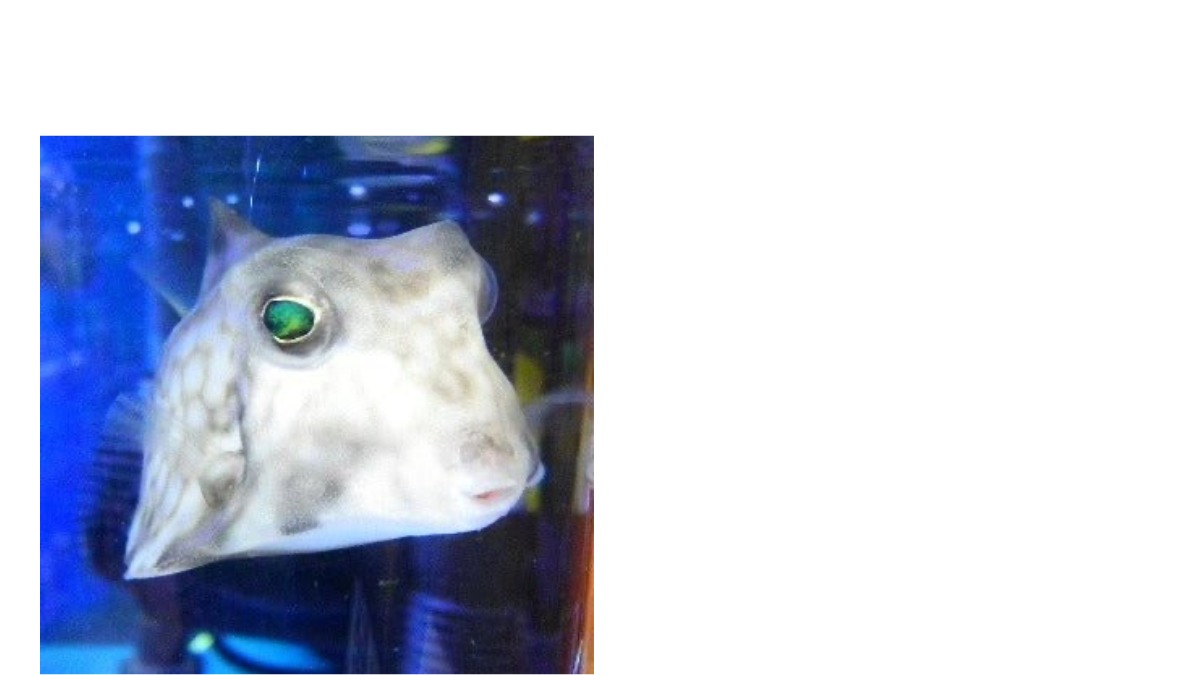
【執筆/コラク】 [問い合わせ先]なし |
コラク氏の説をもっと詳しく知りたい方は・・・
▶▶公式ブログ
ヤマモトタケルノミコト氏の説/卑弥呼はだれなのか! 卑弥呼は天照大神=大日靈女命(おおひるめのみこと)=大宜都比売命?
阿波には天石門別八倉比売神社という延喜式内大社・阿波国一宮があります。そこの本殿の裏に奥ノ院と言われる古墳の後円部の頂上に五角形の祭壇があり卑弥呼の墓であると言われています。この神社は御祭神が大日靈女命、また別名が天照大神と言われ、この説は多くの学者に古くから主張されています。卑弥呼も天照大神も男弟(スサノオ)が重要な役割を持っており、卑弥呼の死の前後に起こったとされる日食と天の岩戸神話の関連性も着目してみると、この神社の近くに箭執神社(やとりじんじゃ): 祭神は櫛岩窓命と豊岩窓命で天石門別神ともいう。
また松熊神社:祭神は手力男命(たぢからお)と天宇受女命(あめのうずめ)も祀られており、天岩戸伝説の主役級が並んでいます。近くの大泉神社に「天の真名井」(古事記・日本書紀でも見られる)と呼ばれる五角形の神聖な井戸があります。天文年間までは十二段の神饌田の泉であったと言われています。またこの気延山周辺には200基以上の古墳があると発表されており、まさに王家の谷のようですね。
また天石門別八倉比売神社御本記には葬儀や当時の風習が記されており、何より、赤珠の印璽/【金印】が埋まっているとの伝承があり、これは『魏志倭人伝』に記されている239年に「親魏倭王」の金印をもらったとされる話とも繋がり、この卑弥呼と八倉比売神社の伝承を重ね合わせることができると思います。発見されれば邪馬台国論争に終止符を打つほどの話ですね。
(余談)さらに中国の目線から見ると、卑弥呼は「鬼道をもって民を治めた」とされる宗教的・政治的指導者としての姿があり、倭国の女王として認められる背景には、中国との外交が可能なほどの政治力と霊的威信を持つ存在であったと考えられます。中国の魏から金印をもらったのは大月氏(クシャーナ朝)1回、倭2回です。もしかすると同じ月氏族に送られたのかもしれません。阿波の神である大宜都比売命(月氏)で穀物の神と言われており、古代では最も大事な神様と言えます。その月氏族と良い関係性を結びたく金印を送ったのでは。この考察は根拠少ないですが検証できる方がいたら宜しくお願い致します。(笑)
まとめ。阿波には古代より「忌部氏」という祭祀氏族がいて、天照大神の神話とも深く関わりがあり、彼らは麻の栽培、織物、神具の奉製などを担い、朝廷の祭祀に欠かせない存在でした。卑弥呼の鬼道にも麻は使われていたと考えると天照大神=卑弥呼ではとここでも色々繋がりますね。皆さんはどう思いますか?


【執筆/ヤマモトタケルノミコト】 [問い合わせ先]heartfull80@gmail.com |
ヤマモトタケルノミコト氏の説をもっと詳しく知りたい方は・・・
▶▶邪馬台国は阿波だった!(YouTube)
▶▶アワテラス歴史研究所アワラボ(Facebook)
▶▶一般財団法人阿波ヤマト財団(公式HP)
三村隆範氏の説/天照大御神と卑弥呼が阿波に居たから証明できる
卑弥呼は日本国の誰に当たるかという問いである。天照大御神は、「古事記」や「日本書紀」等に書かれる日本国の最高神である。一方、卑弥呼は、3世紀の中国の歴史書「三国志『魏志倭人伝』」に記録されている邪馬壹国(やまとこく)の女王である。天照大御神も卑弥呼も阿波に居たということを【卑弥呼と天照大御神】【卑弥呼と台与】【卑弥呼の死と天岩戸隠れ】、この三点をテーマに絞って説明したい。
①【卑弥呼と天照大御神】 天照大御神(あまてらすおおみかみ)は、日本神話に登場する太陽神であり、イザナギ大神 が「小戸の橘」で禊をした時、誕生したと「古事記」に書かれている。イザナギ大神は、天照大御神に『汝は、高天原を知らせ』と命じ高天原、つまり「やまと」の女王になった。 一方、「魏志倭人伝」には、「やまと国(倭国)」は、男王が統治していたが、国内は大いに乱れたため(倭国大乱)、卑弥呼を擁立し安定したと書かれている。天照大御神も卑弥呼も同じく「やまと」を安定させるためであるから同一人物である。一般では、天照大御神が、奈良に居たとは説明しない。九州にいたと言うかもしれないが、九州では、「古事記」の物語のつじつまが合わない。阿波では、それらの説明ができる。
②【卑弥呼と台与】卑弥呼が死に、男王になると再び国は争いが始まったので、卑弥呼の宗女(そうじょ) である台与(とよ)を擁立して国を治めたという。「宗女」とは、「同族の女性」という意味であるから天照大御神の同族の女性である。天照大御神は、「橘の小戸」で生まれた女性で、「橘の小戸」といえば、海神の娘、豊玉毘売(とよたまびめ)が、「橘の小戸」に居ることが、「日本書紀」に書かれている。また、阿波の式内社にのみ二社の豊玉比売神社が平安時代から鎮座している。しかも天石門別豊玉比売神社と「天」を冠していることは、海神の娘が後を継いだ事を表している。阿波でなければ「卑弥呼と台与」が、阿波に居たことを説明できない。
③【卑弥呼の死と天岩戸隠れ】 卑弥呼の死んだ247年と248年の皆既日食があったと天文学者が発表していて、天照大神の天岩戸物語と関連付けられている。 天照大御神と鏡は、密接に関連している。「この鏡を私と思って祀れ」と渡された八咫鏡を持って天孫降臨してくる。卑弥呼も中国から鏡を送られた鏡を配布する。「やまと」は、阿波から始まったからである。

【執筆/三村隆範(みむらたかのり)】
[問い合わせ先]連絡先090-8282-0328(三村) |
三村隆範氏の説をもっと詳しく知りたい方は・・・
▶▶東阿波ケーブルテレビ出演 ~阿波に広がる古事記の世界~ 阿波古代史プロジェクト6回シリーズ 第1回 高天原から伊耶那美眠る高越山(YouTube)
▶▶阿波古事記研究会(Instagram)
▶▶阿波古事記研究会 グループ(Facebook)
テーマ②【完】。
次回のテーマは・・・
【三貴神「スサノオ」「アマテラス」「ツキヨミ」と阿波の関係】
掲載日は2025年8月1日(金)。乞うご期待