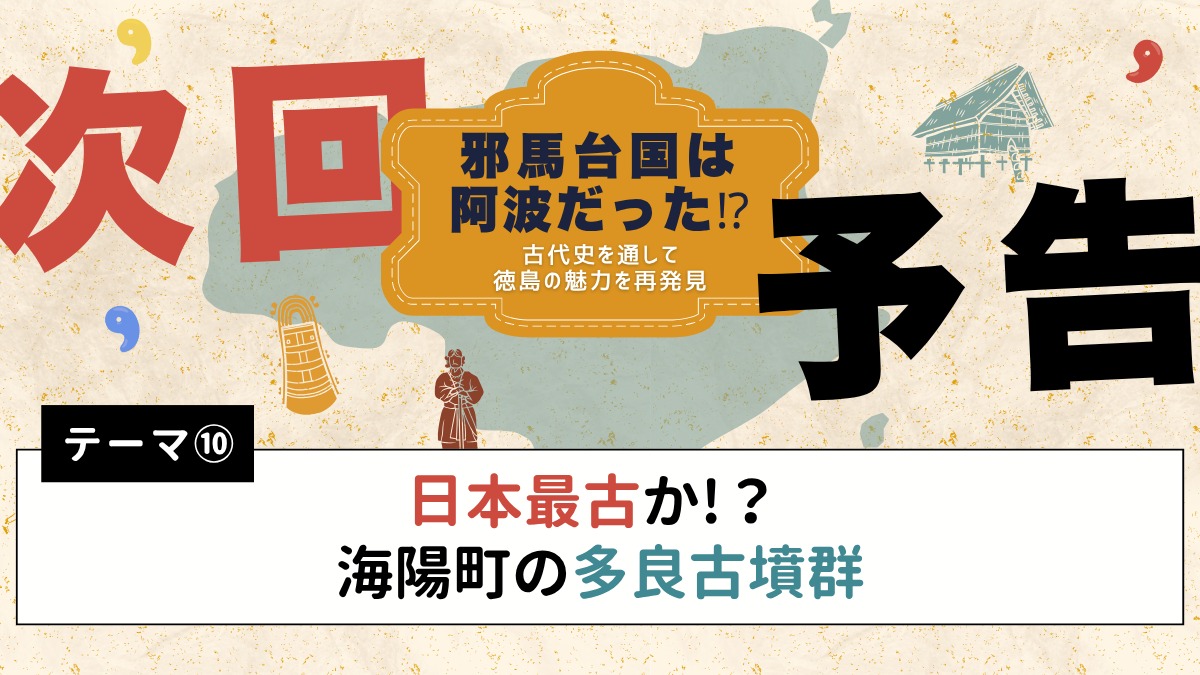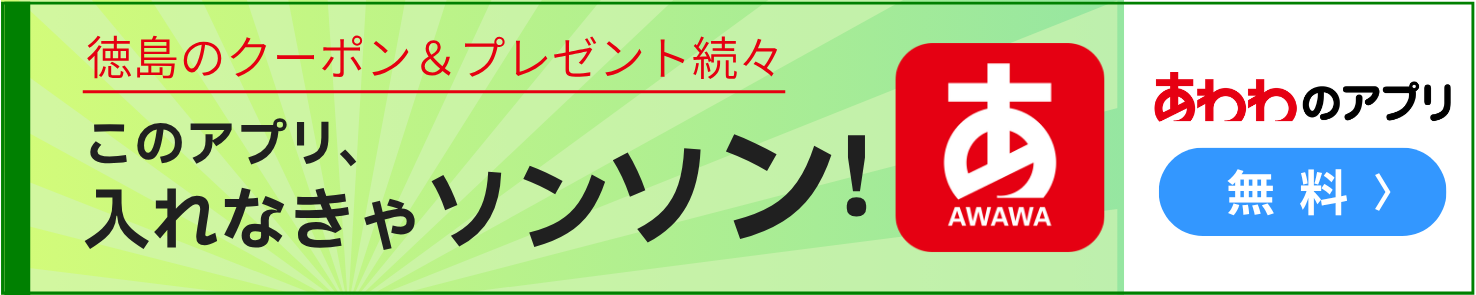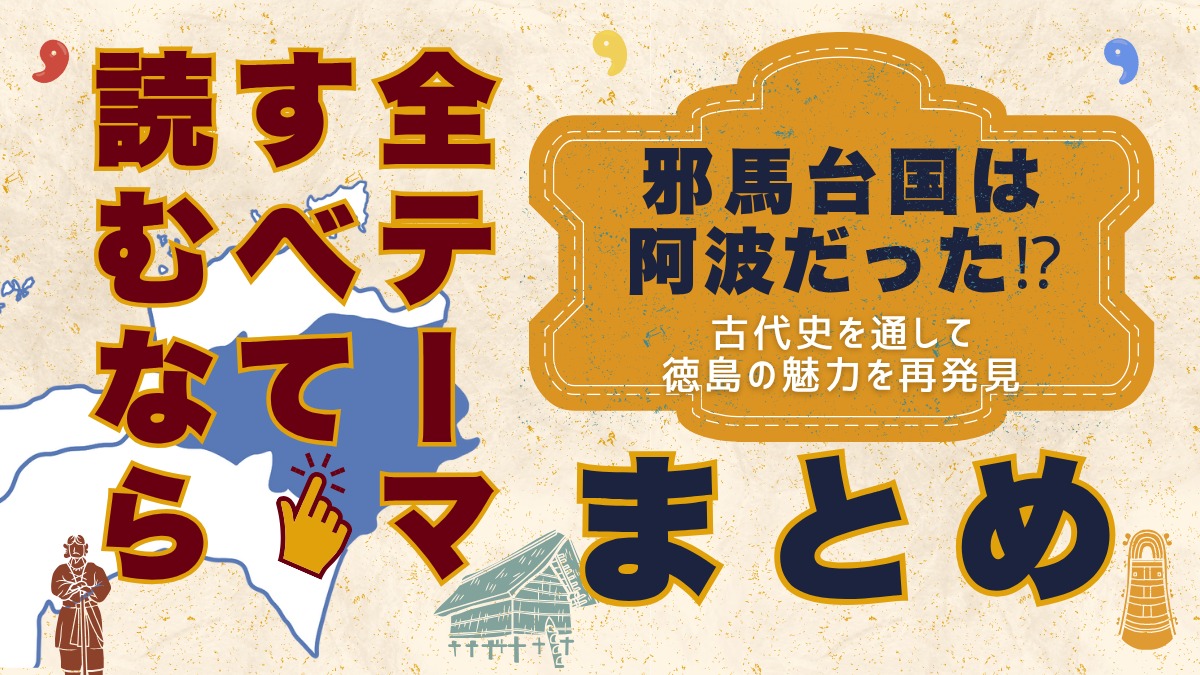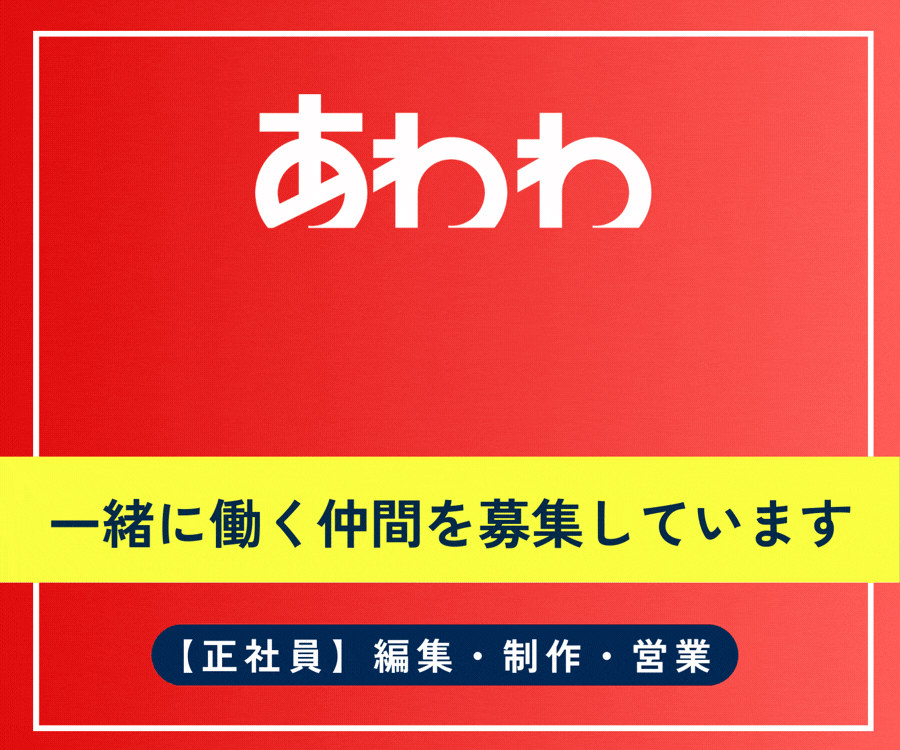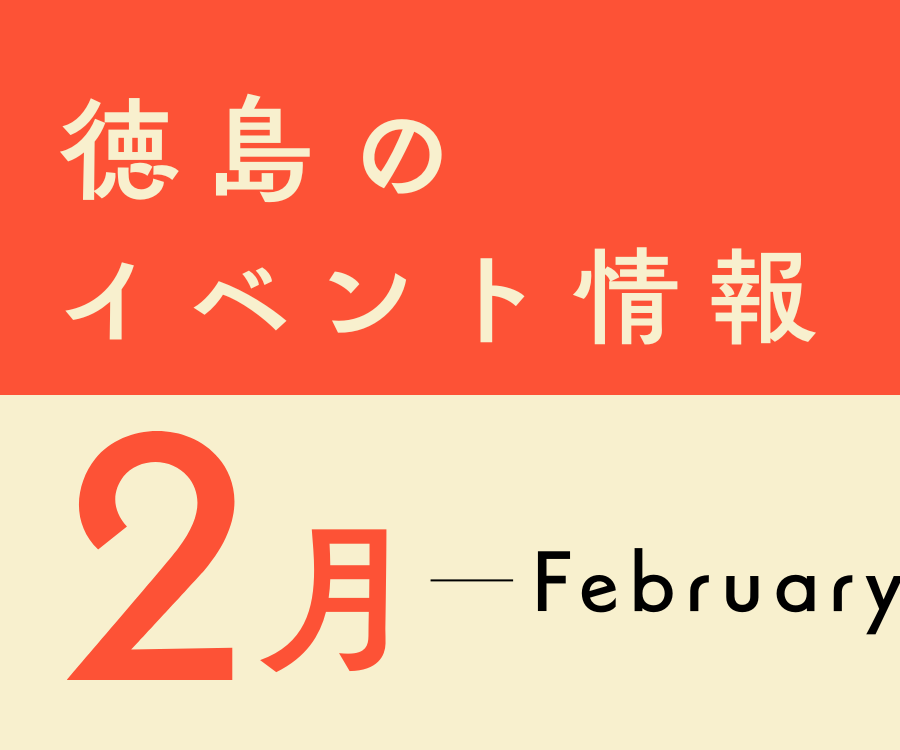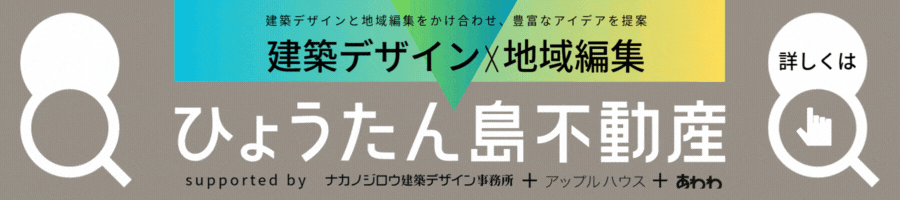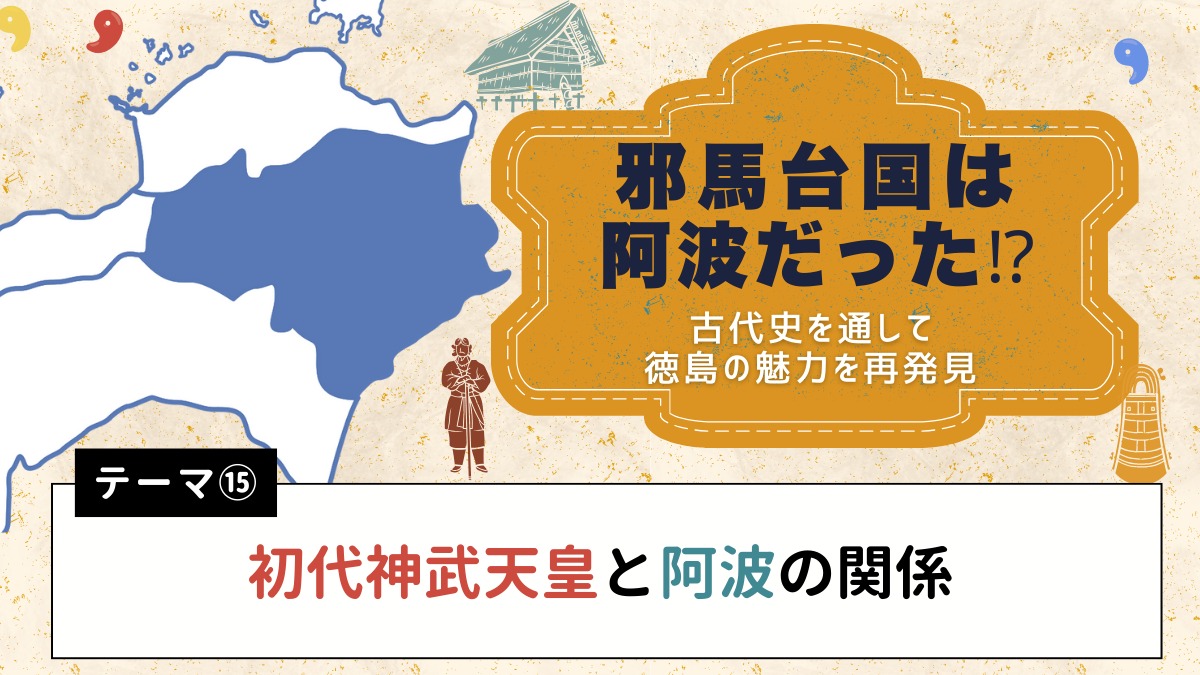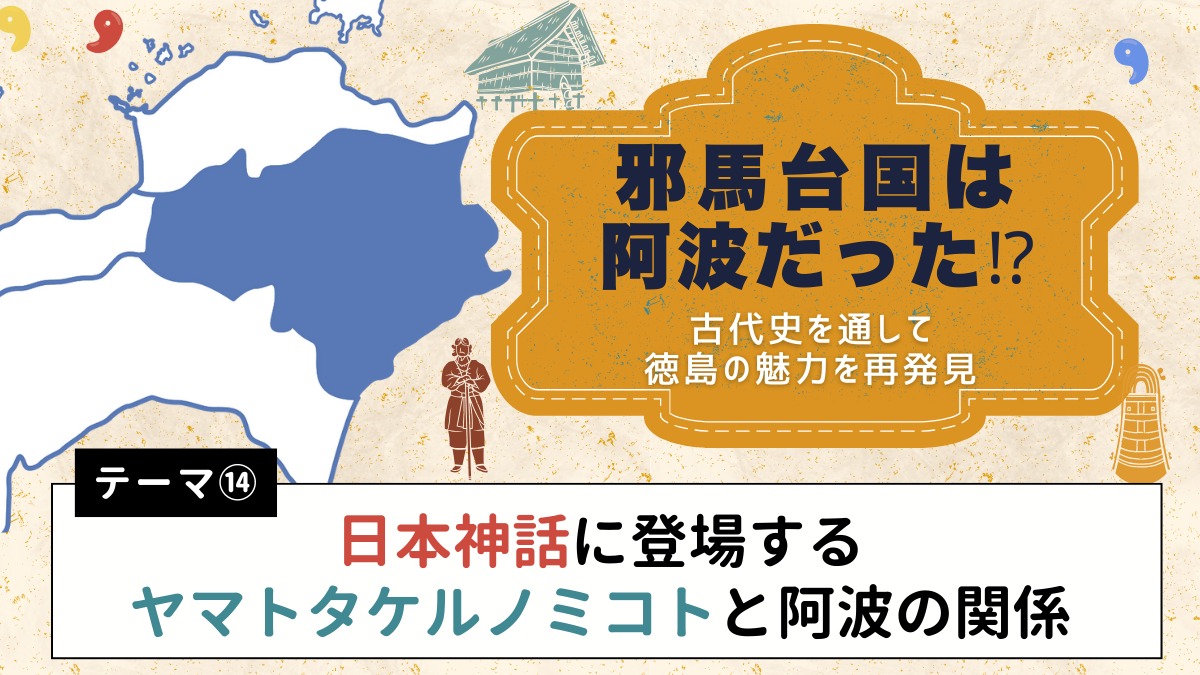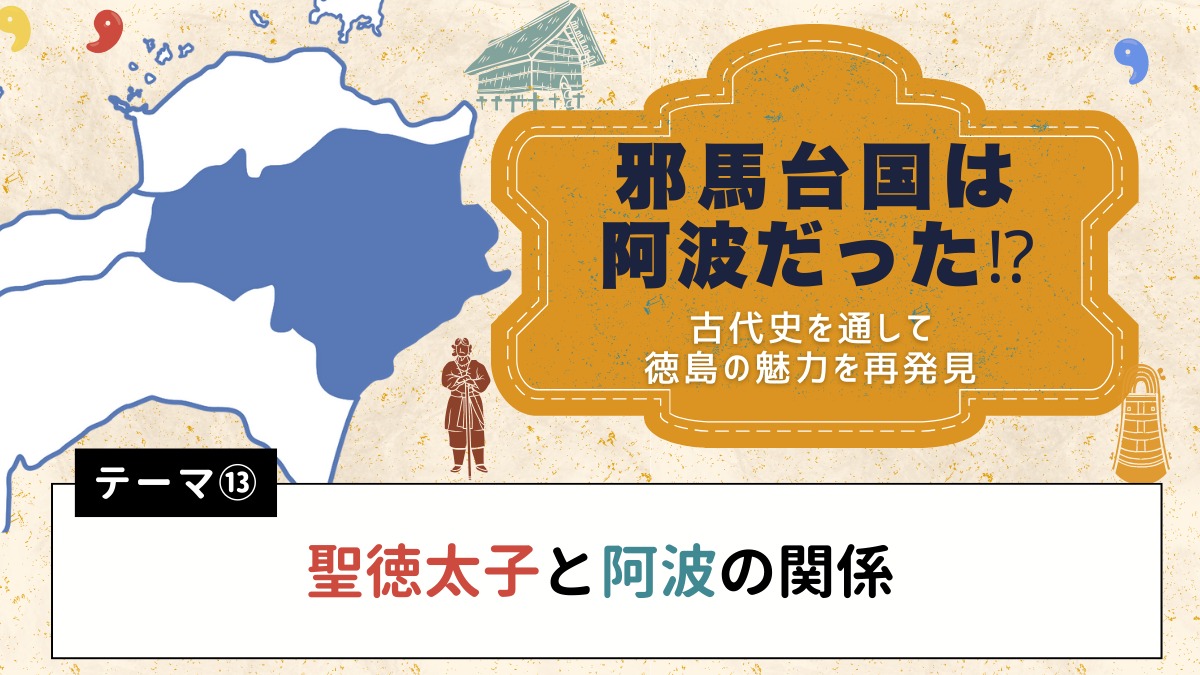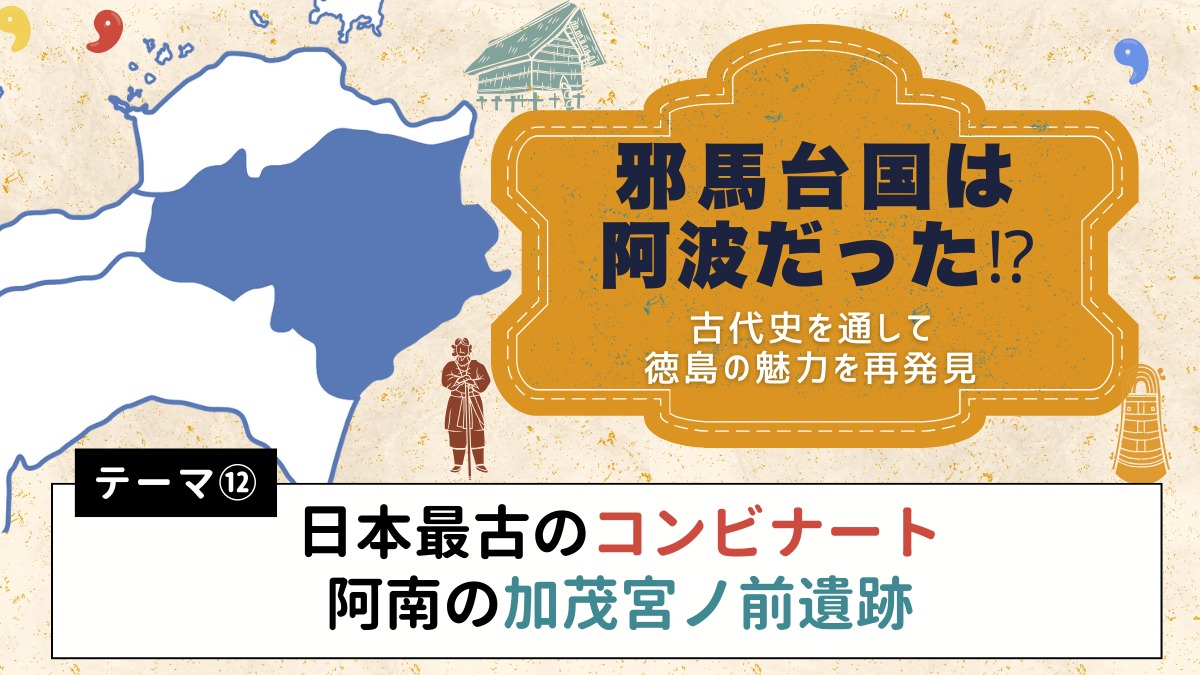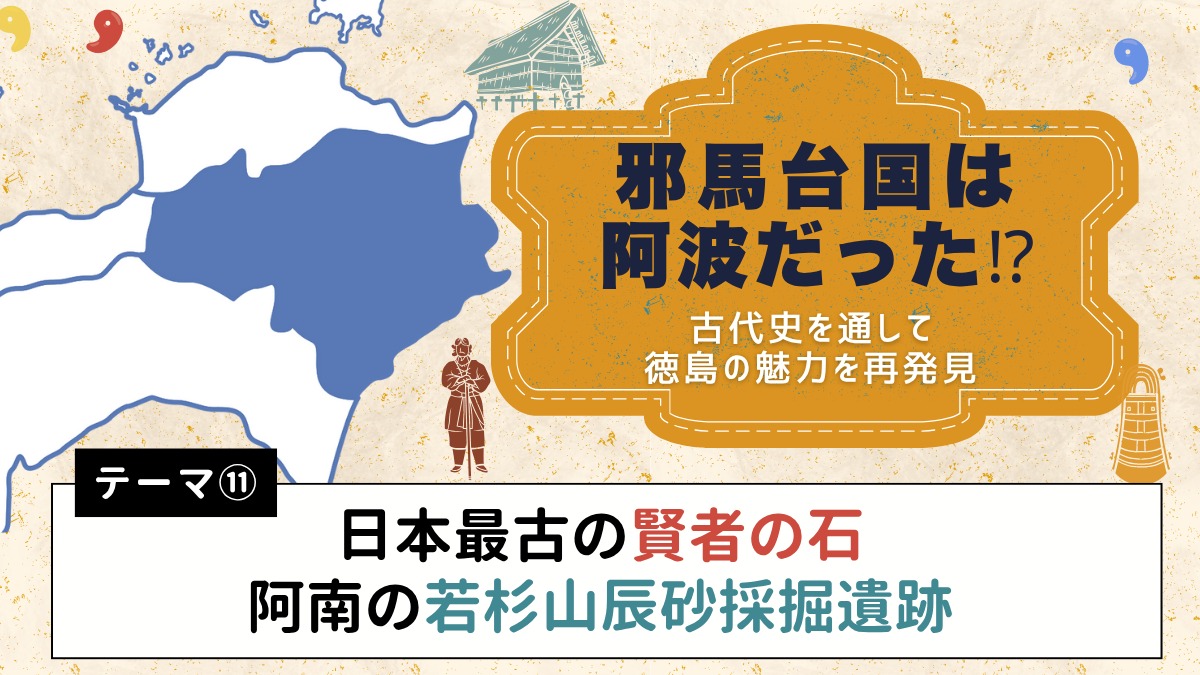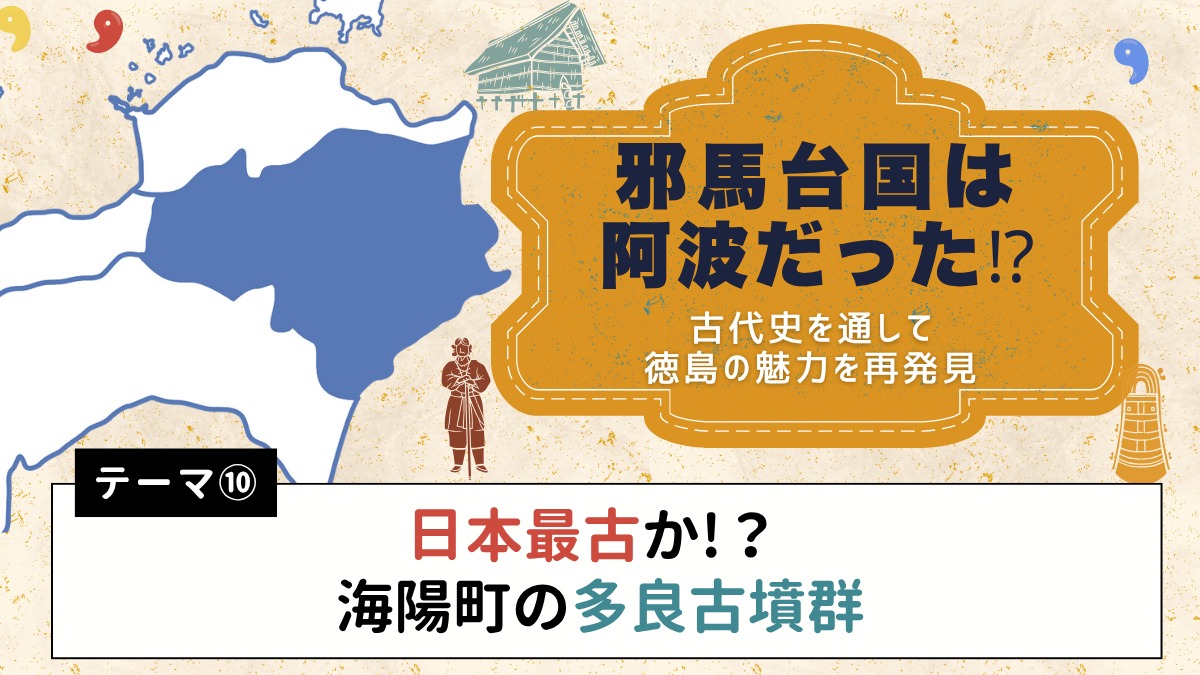2025/11/01 01:00
あわわ編集部
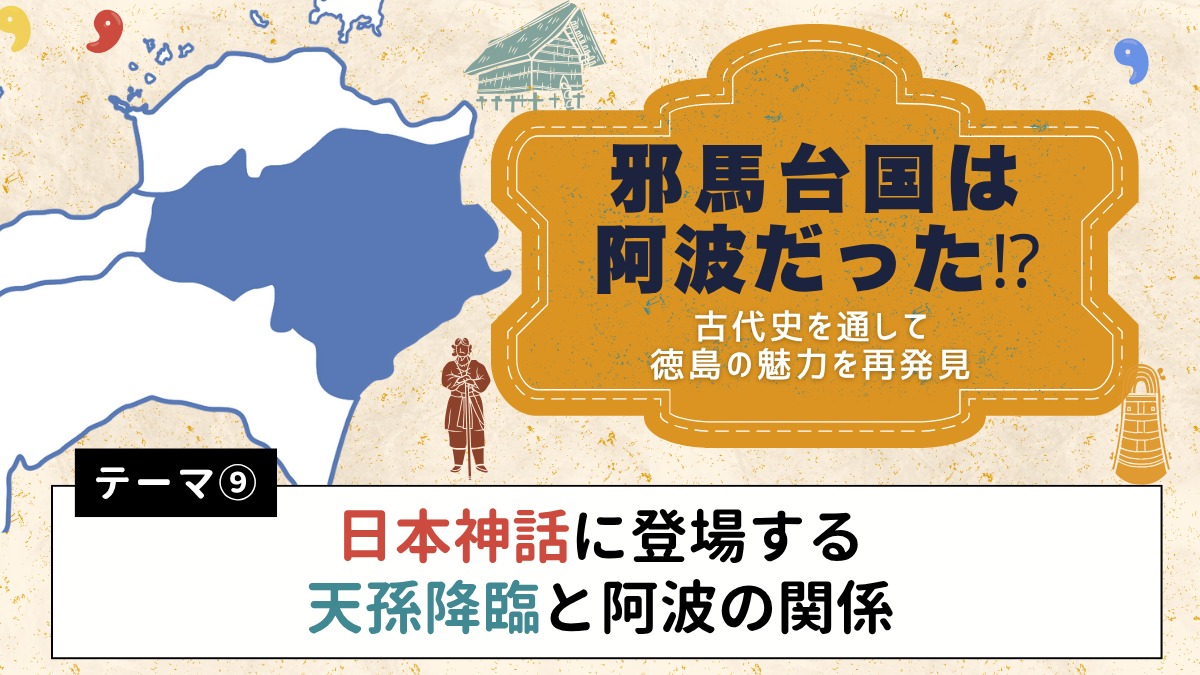
邪馬台国は阿波だった!?【古代史を通して徳島の魅力を再発見】テーマ⑨日本神話に登場する天孫降臨と阿波の関係
小学生の社会の授業で習う、あの「邪馬台国」が阿波徳島にあったかもしれない説が盛り上がっている。魏志倭人伝など各歴史書からも符号する事象が多くあり、邪馬台国阿波説に関する書籍やWEB記事、YouTubeなどで各執筆者が自分の説を論じている。ただ、阿波説は完全一致していなくて(そこがまた歴史ロマンにあふれている!)、それぞれ積み上げてきた研究で自身の説を発信しているのが現状。1800年も前の出来事を完全一致させることはほぼ不可能ということで・・・。それならば!それぞれの論者の説を一同に掲載することで、各説の微妙な違いや逆に一致している点などを比較できるようにしようと、まとめ記事を企画しました。この無謀かつ挑戦的な企画にもかかわらず、快諾していただいた執筆者はなんと8名も!毎回のテーマごとにエントリーして執筆してもらうスタイルでまとめていきます(エントリーしないテーマのときもあります)。それぞれが論じる内容を読み比べ、納得する説をお好みでチョイスしていってください。なお、当企画は阿波の古代史を通して徳島の魅力を再発見するというのがミッションなので、邪馬台国以外のテーマも登場予定です。
※注※
この連載コーナーは、各執筆者の考え・主張をまとめたもので、あわわWEB編集部として特定の説を支持する立場でないことをご理解ください。内容に関する問い合わせなどにつきましては、各執筆者に直接連絡してください。
また、本記事の内容は著作権法により保護されています。無断での転載、複製、改変、及び二次利用は固く禁じております。記事自体のシェアは大歓迎です。
邪馬台国は阿波だった!?テーマ⑨日本神話に登場する天孫降臨と阿波の関係
通説
日本神話に登場する天孫降臨
天孫降臨(てんそんこうりん)とは、『記紀(古事記と日本書紀)』に記された日本神話。 邇邇芸命(ににぎのみこと)が、葦原の中津国を治めるために、高天原から筑紫の日向の襲の高千穂峰へ天降(あまくだった)こと。
天照大御神と高木神(高御産巣日神)は、天照大御神の子である天忍穂耳命に、「葦原中国平定が終わったので、以前に委任した通りに、天降って葦原中国を治めなさい」と言った。 天忍穂耳命は、「天降りの準備をしている間に子の邇邇芸命が生まれたので、この子を降すべきでしょう」と答えた。邇邇芸命は、天忍穂耳命と高木神の娘の万幡豊秋津師比売命との間の子である。それで二神は、邇邇芸命に葦原の中つ国の統治を委任し天降りを命じた。
【猿田毘古】
邇邇芸命が天降りをしようとすると、天の八衢(やちまた)に、高天原から葦原の中つ国までを照らす神がいた。そこで天照大御神と高木神は天宇受売命に、その神に誰なのか尋ねるよう命じた。その神は国津神の猿田毘古神で、天津神の御子が天降りすると聞き先導のため迎えに来たのであった。
【天孫降臨】
邇邇芸命の天降りに、天児屋命、布刀玉命、天宇受売命、伊斯許理度売命、玉祖命の五伴緒(いつとものお)が従うことになった。 さらに、天照大御神は三種の神器と思金神、手力男神、天石門別神を副え、「この鏡を私の御魂と思って、私を拝むように敬い祀りなさい。思金神は祭祀を取り扱い神宮の政務を行いなさい」と言った。八咫鏡と思金神は伊勢神宮に祀ってある。登由宇気神は伊勢神宮の外宮に鎮座する。
天石門別神は、別名を櫛石窓神、または豊石窓神と言い、御門の神である。手力男神は佐那那県(さなながた)に鎮座する。 天児屋命は中臣連(なかとみのむらじら)の、布刀玉命は忌部首(いむべのおびとら)の、天宇受売命は猿女君(さるめのきみら)の、伊斯許理度売命は作鏡連(かがみつくりのむらじら)の、玉祖命は玉祖連(たまのおやのむらじら)の、それぞれ祖神である。
邇邇芸命は高天原を離れ、天の浮橋から浮島に立ち、筑紫の日向の高千穂の久士布流多気(くじふるたけ)に天降った。天忍日命と天津久米命が武装して先導した。天忍日命は大伴連(おほとものむらじら)の、天津久米命は久米直(くめのあたひら)の、それぞれ祖神である。邇邇芸命は「この地は韓国からくにに向かい、笠沙かささの岬まで真の道が通じていて、朝日のよく射す国、夕日のよく照る国である。それで、ここはとても良い土地である」と言って、そこに宮殿を建てて住むことにした。
●三村隆範氏の説
●島勝伸一氏の説
●藤井榮氏の説
●オキタリュウイチ氏の説 (今回は休載)
●恋塚建生氏の説
●ANYA氏の説
●コラク氏の説
●ヤマモトタケルノミコト氏の説
三村隆範氏の説/日本神話に登場する天孫降臨と阿波の関係
【やまと(弥生時代)時代】
一般に、縄文時代・弥生時代と歴史を区分しているが、弥生時代とは、「やまと文化」の始まり該当するから、「『やまと』は、阿波から始まった」ということが、「古事記」を読めばわかってくるのである。 「古事記」は、高天原〔やまと〕と出雲国を往来する物語が書かれている。従来解釈されているように、荒唐無稽のおとぎ話ではない。実際にあった話が語られているので、読めば読むほど事実が浮かんでくるのである。
【 高天原 〔やまと〕 】
天孫降臨は、高天原から出雲国に降臨してくる物語ですが、高天原とは「やまと」のことです。なぜ「やまと」であるかということは、先でも書きましたが、大和(やまと)から続く天皇陛下が、天皇に即位する式典「践祚大嘗祭(せんそだいじょうさい)」を執り行う際に、「麁服(あらたえ)」を、なぜ奈良県(大和) 製作せず、徳島県の山間部である徳島県美馬市木屋平から製作し運ばれているのか?
これを知るだけで賢明な読者なら気がつくと思う。これは平安時代に編纂された「延喜式神名帳」を見ても「阿波の忌部の織たるもの」と書かれているので、「麁服」古代より続いている事であるから、阿波の山間部が高天原〔やまと〕の始まる地であることを物語っている。その高天原〔やまと〕から天照大御神の孫のニニギノ命が出雲〔吉野川下流〕に降りて来るのが、天孫降臨の物語である。
【出雲国】
「古事記」に書かれる出雲国は、「葦原中国(あしはらなかのくに)」であり、天孫降臨してくる出雲国は「豊葦原水穂国(とよあしはらみずほのくに)」である。この記述からみても葦の生えた海岸部であることが思い浮かぶであろう。そんな地形は、日本国中いたるところにあるであろうが、天孫降臨する地は、出雲であり葦原中国の中にある豊葦原瑞穂国に天孫降臨してくるのである。
「古事記」の中に書かれる出雲国は、これまで何度も書いてきたように、徳島県の海岸部のことであり、豊葦原瑞穂の国とは、葦原が豊かに広がる大河吉野川の下流域のことである。
出雲の神様「大国主(おおくにぬし)神」は、阿南市長生町に八桙神社(やほこじんじゃ)が鎮座している。
隣町には、大国主神の子供である「事代主(ことしろぬし)神」が「生夷神社(いくい)」鎮座して、石井町には、「建御名方神(たけみなかた)」が鎮座している。「古事記」に書かれる出雲の神が徳島県の海岸部に鎮座している。これは、 平安時代の「延喜式神名帳」にも記録されていることで、島根県には記録がない。いくら出雲大社という大きな社があっても、肝心の「古事記」には書かれていないことである。
大国主命は、「そこに大きな社(神社)を建ててください」といった神社は、徳島市国府町に鎮座ずる式内社「大御和神社」のことである。平安時代に編纂された「延喜式神名帳」を見ても「大御和神社」は、阿波に一社のみ鎮座している。
このように「古事記」は、阿波で繰り広げられた話を記録したものであるから、読めば読むほど話が深まってくる。研究調査もまだまだ初段階であり、今後若い研究者が現れ新発見される日を楽しみに期待している。若い研究者が現れ新発見される日を楽しみに期待している。

▲高天原から出雲に天孫降臨。

【執筆/三村隆範(みむらたかのり)】
[問い合わせ先]連絡先090-8282-0328(三村) |
三村隆範氏の説をもっと詳しく知りたい方は・・・
▶▶東阿波ケーブルテレビ出演 ~阿波に広がる古事記の世界~ 阿波古代史プロジェクト6回シリーズ 第1回 高天原から伊耶那美眠る高越山(YouTube)
▶▶阿波古事記研究会(Instagram)
▶▶阿波古事記研究会 グループ(Facebook)
島勝伸一氏の説/天孫降臨と阿波の関係
こんにちは!前回の魏志倭人伝中のやまと朝廷の皇祖天照大神(女王卑弥呼)の父伊邪那岐命が黄泉の国から逃げ帰り、阿南市桑野川が橘湾に注ぐあたりで天照、月読、素戔嗚の三貴神をお産みになった。伊邪那岐命より天照大神は高天の原を、素戔嗚は出雲(阿波の国、東海岸から海部川河口部)を治めるように命ぜられた。ちなみに、伊邪那岐・伊邪那美は天つ神より縄文海進で海となっていた「漂える平地部(出雲地方や吉野川、那賀川、桑野川、勝浦川、海部川流域)を修め創り固めよ」と命ぜられ、邪馬台国の卑弥呼の宮居のあった神山町から吉野川流域東みよし町(式内社天橋立神社)へ下り、吉野川河口鳴門まで出た。
そこで神話が生まれ、鳴門の大渦を見て、オノコロ島をはじめ、大地を固め、大自然の神々を産み、九州、隠岐や対馬まで影響力を伸ばしていった。 そこで今回は、高天の原の天照大神が「豊葦原瑞穂の国は我が御子・天忍穂耳命の知らす国ぞ」と出雲を治めてきた素戔嗚命の子孫大国主神側への「国譲り」を要求、その成立後、天照大神の孫邇邇芸命が出雲に降臨する物語である。が、この国譲り交渉は難航した。第一の使者天菩比神は大国主に媚て、3年間復奏しなかったので、第二の使者天若日子を遣わすが、また大国主の娘下照比賣を娶り8年間復奏しなかった。ついに建御雷神に天鳥船神をつけて遣わした。この二神の武功で、大国主命側の事代主は服従、建御名方神は抵抗したが負けて、信濃の国(長野県)まで逃げ、命乞いをし、後世「戦の神」として諏訪神社に収まる。
ついに大国主命は、長子事代主命に出雲の国の全ての神を統率させ天孫の神に仕えさせることを誓った。 そこで、天照大神は御子天忍穂耳命に「葦原中国に下りて治めよ」と命じたが「僕は下る用意をしていたが、その間に二人の子供が生まれた。第一子を天火明神(饒速日命)と第二子天津日高日子番能邇邇芸命と言い、この第二を降らすべき、と奉じ、天照大神も承認した。
そこで邇邇芸命は天宇受賣神に天降る案内者は誰ぞある、問えば国津神猿田毘古神がこれを聞きつけ、御前に仕え奉る、と申し出た。
天照大神は天孫邇邇芸命に「八尺の勾玉、鏡、草薙剣」を与え、思金命に「鏡はわが御霊として拝き祀れ」と祭祀・政せよと命じた。随員に天児屋命、布刀玉命(忌部の祖:政・祭祀に必要な様々な準備をする氏)、天宇受賣神、伊斯許理度賣命,玉祖命の五神と常世思金神、手力男神、天石門別神を副え降臨させた。(よって後の世、藤原不比等が古事記を編集した際、天児屋命を中臣の祖とし、中臣氏が祭祀を司る氏としたのは捏造である)

【執筆/島勝伸一(しまかつしんいち)】 [問い合わせ先]080-3533-5146(島勝) |
島勝伸一氏の説をもっと詳しく知りたい方は・・・
▶▶島勝伸一解説 岡元雄作監督作品 ドキュメント映画『ルーツ オブ ザ エンペラー』令和6年6月27日 四国古代史サミット東京(YouTube)
藤井榮氏の説/邇邇芸命と木花之佐久夜比売(神阿多都比売)の悲恋
●(アレ:阿礼)ウズメや、此度のテーマもお前に縁ある話じゃぞ。 ◎(ウズメ:宇受売)おじ様、何のこと? ●(アレ)大御神のお孫ニニギ様がここ「葦原中つ国」へ降りて来なさった時の話じゃ。 ◎(ウズメ)何で私に関係があるの? ●(アレ)ありりゃ、言い伝えを聞いておらんのか。ニニギ様が降りて来られた時先導をしたのがお前のご先祖じゃろうが。 ◎(ウズメ)ふう~ん、そうなの。 ●(アレ)頼りないのう。お前のご先祖のアメノウズメ様がニニギ様ご一行の先頭に立って「葦原中つ国」からご一行を出迎え道案内をしたサルタビコ(猿田毘古)様と向き合ってやり取りをしたのが縁で結ばれたじゃろう。そうして長い歳月が経って今ここにお前がおるんじゃろうが。お前は人から“猿女君(さるめのきみ)”とも呼ばれとるじゃろう。それはニニギ様がアメノウズメ様にそう名乗るようにと仰せられたからなのじゃ。お前の遠いご先祖様はアメノウズメ様だけではないぞよ。サルタビコ様もお前のご先祖様じゃからの。
◎(ウズメ)おじ様よく覚えていらっしゃること! ●(アレ)当たり前じゃ。“ふることぶみ(古事記)”を編纂するとき、ヤスマロ(安万侶)に何度誦み聞かせたことか。‥‥ ◎(ウズメ)おじ様、ところでニニギ様が「高天原(たかまのはら)」から降りて来られた地、私達の言ってる“天孫降臨地”ってどこなの? ●(アレ)はて? ワシは前にも言ったとおり、昔からの云い伝え・記録や人からの話を暗誦しただけじゃからのう。 ◎(ウズメ)はいはい、ヤスマロ様の文でしょ、おじ様。この文箱の中のどれかなのよねえ。‥‥あっ、あったわ! ●(アレ)あったか、読んどくれ。
『(ヤスマロ)以前のテーマ「天の石屋戸(あめのいはやと)」の末尾で後の世の古代史塾代表が述べているとおり、高天原は剣山系東端の佐那河内(さなごうち)、より具体的には佐那河内村を東西に走るなだらかな高峰、高天原伝承“天嶺(てんれい)”と呼ばれる「大川原高原(おおがわらこうげん)」:元「王ヶ原」辺りで、天照大御神と高木神の仰せにより邇邇芸命(ニニギノミコト)はここ佐那河内村「王ヶ原」たる高天原を離れて「高千穂(たかちほ)のくじふる嶺(たけ)」(高越山(こおつざん)=木綿麻山(ゆうまやま)=摩尼珠山(まにしゅざん)1,133m):吉野川市山川町木綿麻山)に天降りをされ、宮柱を立てて宮殿に住まわれたのでした。』
◆太安万侶ほどの方から名指しを受ける栄に浴しましたが、天孫ニニギノミコトの降臨地は古事記序文冒頭の件に「高千嶺(たかちほのたけ)」とあり、また天孫降臨条に「高千穂のくじふる嶺(たけ)」とあることで分かるように吉野川市山川町の“阿波富士”高越山(こおつざん)のことです。「たかち」の「嶺(山)」で、高越山も「たかち」の山である「たかちほ」を後世に伝えるため「高越」として表したものかとも考えられます。 ◆実際の降臨地は、高越山の麓付近の「添山(そうやま)」(「神明(しんめい)神社」の小山)であると考えます。というのは、日本書紀神代下九段一書の第六に記されている『降到(あまくだ)りましし処(ところ)をば、呼(い)ひて日向(ひむか)の襲(そ)の高千穂の添山峯(そほりのやまのたけ)と曰ふ。』とも一致し、また「白人(しらひと)神社」の中世の記録にある「添山」にも合致するからです。
◆さて降臨され、ここを拠点として葦原中つ国への支配を広げる中で吉野川下流北岸「大山」の麓で“麗しき美人(うるわしきおとめ)”木花之佐久夜比売(コノハナサクヤビメ)と出逢ったニニギノミコトは、結婚の申し出をして姫の父大山津見神に喜ばれて一夜の交わりをされたところ、コノハナサクヤビメがたちまち身ごもったためこれを疑われたことを晴らすため、姫は出入り口の無い産殿を造って土ですっかり塗り塞ぎ、その中で産殿に火をつけて子を生んだのでした。
◆生まれた3人の皇子「火照命(海幸彦)」・「火須勢理命」・「火遠理命(山幸彦)」と一緒にいた妃コノハナサクヤビメでしたが、夫ニニギノミコトに会いたい思いがつのり、死期を悟ると生地の「阿多(あた):板野」から夫の宮「白人神社」(美馬市穴吹町口山宮内)辺りまで伯伎(ははき:端々岐)を上り、宮までたどり着くと血を吐きながら命絶えました。 ◆ニニギノミコトの宮処ともいわれる「白人神社」の横、穴吹川対岸北には妃を祀る「新宮(しんぐう)神社」が鎮座しており、この辺りは「血野(ちの)」(現在「知野」)と呼ばれています。 ◆ニニギノミコトは、「白人神社」のご祭神としてすぐ南上方の“殯(もがり)の宮跡”「神明神社」(五社三門」(いわさか))とともに妃の「新宮神社」を見通すようにして眠られています。 ◆命と妃の悲しい物語は後の世に語り継がれるうちに広くこの地方に“お花権現”信仰として残されており、今も“白人はん、お花はん”と親しみを込めて呼ばれているのです。 ◆皆さんも一度はここを訪ねて往古を偲んでみては如何でしょうか。
【参照リンク】
① YouTubeチャンネル古代史塾 「薄幸悲運の姫コノハナサクヤヒメ」(古代史解説第10回)
②小著『古代史入門』137~140頁・同『甦る皇都阿波(ヤマト)への旅』テーマ11(46~49頁)・テーマ28(115~122)(両著ともAmazon電子書籍・印刷本)

▲新宮神社から神明・白人神社方向を見る。

【執筆/藤井榮(ふじいさかえ)】 [問い合わせ先]sakae-f-1949@ma.pikara.ne.jp |
藤井榮氏の説をもっと詳しく知りたい方は・・・
▶▶古代史塾(公式HP)
▶▶古代史塾(YouTube)
オキタリュウイチ氏の説/
(編集部注)
オキタ氏は、今テーマにつきましてはテーマの内容に鑑み、休載となりました。
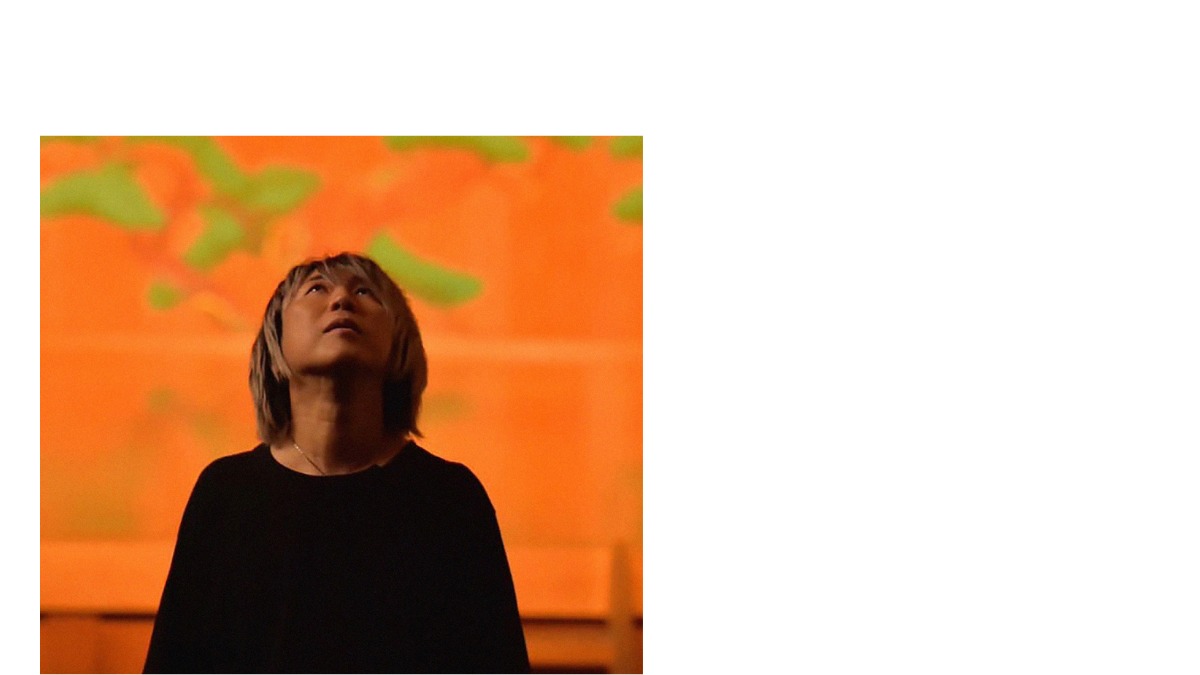
【執筆/オキタリュウイチ】 [問い合わせ先]office@deepbranding.jp |
オキタリュウイチ氏の説をもっと詳しく知りたい方は・・・
▶▶公式ホームページ
恋塚建生氏の説/徳島の地名由来は、天孫降臨の場所ではないか?
高千穂とはニニギノミコトが、降臨した場所であるが、古事記原文には「竺紫日向之高千穂之久士布流多氣」と記述されている。これも、漢字の共通性からその場所は特定できるのだが、高千穂ではなく、久士布流多氣にその答えが書いてある。
久士=櫛で=霊妙な布=太、流=龍、多氣=岳で太龍岳となりロープウエイで有名な、そう『太龍寺山』がその答えである。では高千穂とは何か?それは一言で言うと比喩でしかない。「高さが千の穂」の意味で、稲の草丈(0.6)☓1、000=600mを表現している。それと竺紫の意味に触れよう。竺紫の竺は本来(ちく)とは読まない、竺は篤の簡略された異体字であるから(とく)と読むのが正しく、「ちく」と読み始めたのは、おそらく後に日本書紀の記述、筑紫日向・・・と混同してしまったからではないだろうか?では紫(し)の意味とは何か?それは臙脂のことで、水銀朱の色や・高貴な色を表現しているのではないだろうか。すなわち、竺紫(とくし)とは現在の「加茂谷地区」を表していて、当たっているか間違っているかはわからないが、竺(篤)紫が徳島の地名由来ではないか?と我々は考えています。
これは日本人のほとんどが知らないというか、学者がそれを隠しているとしか考えられないのだが、竺紫は、中国の正史「佛祖統紀」に「竺紫城」という固有名詞で記述されていて、驚くなかれ日本の皇祖がそこに居住していたことも書かれている。また、佛祖統紀には弘法大師・空海のことも記述されているが、その空海が書き残した、「太龍寺縁起」にも太龍寺に皇祖が居住していたことがわかる内容が示されている。ただし、太龍寺縁起は偽書であるというのが一般的解釈のようで、偽書である根拠はなにか?それを私たちは知らない。
最後に、いわゆる高千穂の場所の比定地は全国にもあるようだが、私達は、古事記においてこの場所を間違えると、古事記の読み解きはでないこともわかった。 すなわち、大げさに言うと、日本の古代史は永久にわからないままであると言ってもよい。だが逆に、高千穂がわかると、すらすらと古事記が読み解けることも私達は、理解できるようになってきたのである。

▲太龍寺ロープウェイ。
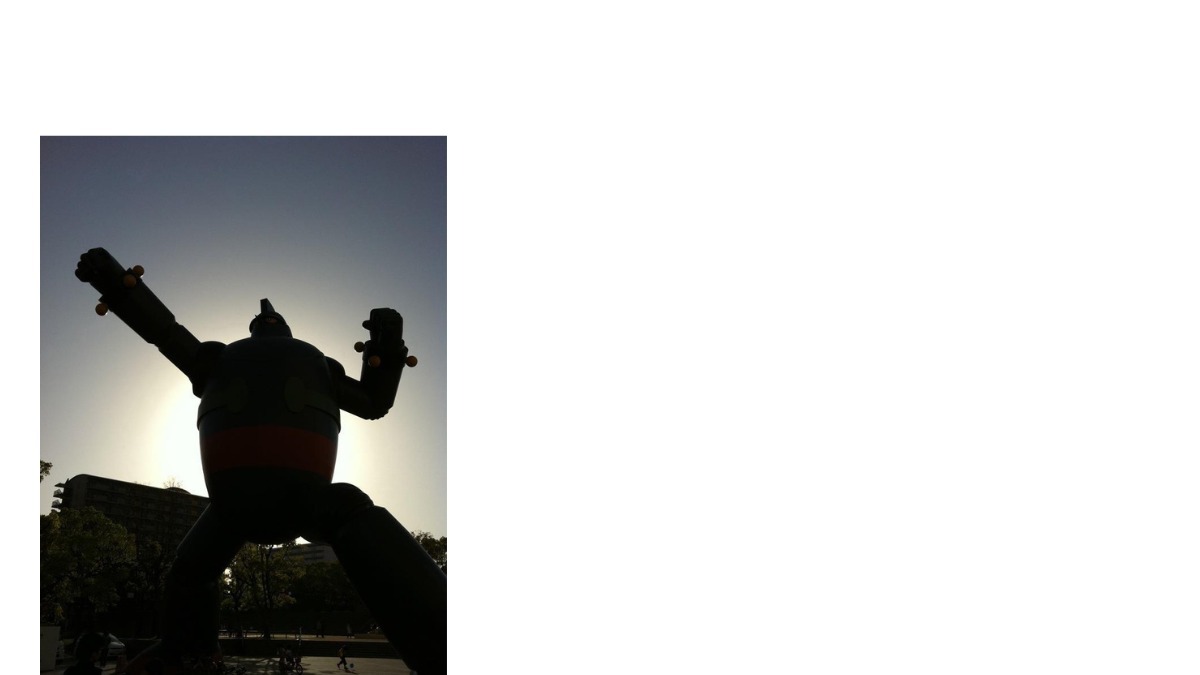
【執筆/恋塚建生(こいづかたけう)】 [問い合わせ先]ogenkisama0@gmail.com |
恋塚建生氏の説をもっと詳しく知りたい方は・・・
▶▶魏志倭人伝を最新技術で読み解いた!(YouTube)
ANYA氏の説/阿波で繰り広げられる神話の舞台
阿波山間部にあった高天原からイザナギ、イザナミはオノゴロ島に降臨し、最初の拠点である蛭子を作ります。グーグルマップで現在の吉野川橋を拡大して見てください、川の中、左側に蛭子の地名が浮かび上がってきます。しかし蛭子は洪水などで流れてしまい、次に淡嶋を作ります。吉野川に善入寺島が有りますが、ここは昔、淡嶋と呼ばれていました。おそらくこの辺りに淡嶋を造り開拓したのだと考えられます。
淡嶋から興った国創りは、やがて葦原が広大に広がる吉野川一帯から拡大し、文字通り葦原水穂国になります。しかし南部の葦原中国は、やがて国津神の領土になってしまいました。そこで天津神たちはニニギを筆頭に眉山から南の葦原中国に天孫降臨し、海陽町那佐の浜で国譲り交渉に成功します。この葦原中国の名前からも、後の阿波南部のナガコクになったのだと考えられます。
皇室には古来から、男児だけが行う深曽木の儀という謎に満ちた儀式が有ります。 右手に桧扇、左手に松と橘を持ち、碁盤の上から“ぴょん”と南側を向いて飛び降りるのです。その碁盤の上にはなぜか青石が二個置かれています。この右手に持つ檜扇ですが、現在は扇の檜扇を使用していますが、植物にも檜扇が有ります。扇を開いたような葉が特徴で、古代には悪霊退散に用いられ、現在も祇園祭には欠かせない、“祭花”として檜扇が配られたりもします。なのでおそらく古代の深曽木の儀では、この檜扇を右手に持っていたと考えられます。
そして、なんとこの植物の檜扇の日本一の生産地は、高天原だと考えられる阿波神山なのです。
つまり、青石は有名な阿波の青石、左手には阿波特産の橘の木、右手には日本一の阿波神山のヒオウギ、そして碁盤は高天原から下った最初の場所である眉山という事になり、この儀式は天孫降臨を伝えていると考えられます。 オノゴロ島の漢字は、古事記では「淤能碁呂島」と表記されます。碁盤の碁の字がちゃんと使われているのです。
眉山は、オノゴロ島であり、天孫降臨の場所でも有るという事ではないでしょうか。 碁の始まりは中国やインド チベットなどと言われており、原型は4000年前と、とても古く、最初は天文や暦や易に用いられたとも言われています。やはり天津神のルーツは、そういう事なのかもしれません。
*①/YouTube ANYAチャンネル107参照

【執筆/ANYA(アンヤ)】 [問い合わせ先]anyautb@gmail.com |
ANYA氏の説をもっと詳しく知りたい方は・・・
▶▶ANYAチャンネル(YouTube)
コラク氏の説/ニニギが天下った出雲の重要拠点
天孫降臨を語る前にまずはそこに至る経緯となる「国譲り」について触れておきたい。 国譲りは高天原を治めていたアマテラスの子孫が葦原中国を統治すべきとし、大国主に葦原中国を譲るよう使者を出雲の伊那佐之小濱に派遣し交渉を行った説話だ。
この伊那佐に比定されるのが、好字二字令後「那佐」と呼ばれる海陽町那佐と推定する。 しじみの産地で有名な宍道湖のある島根県の『出雲国風土記』によると、船に乗ってやって来た阿波枳閉委奈佐比古命という神が和奈佐神社にてお祀りされている。神名の意は「阿波から来経(やって来た)委(わ)奈佐の比古(おとこ)」だ。
また『播磨国風土記』志深(しじみ)の里の条に、17代履中天皇が阿波国和那散 (わなさ)でしじみ貝を食べた事にちなんで宍粟の地名が付いたとの伝承を記す。即ちこれらの起こりが現在の那佐宍喰である。
『古事記』国譲りの場面では「十拳剣を抜き、波の穂に逆にして立て」との記述があるが、『阿波国風土記』逸文にも「奈佐と云ふ由は、其の浦の波の音止む時なし。依りて奈佐と云ふ」とあり、那佐半島はまさに剣形であり、傍らには剣八幡宮も鎮座する。
これらを集合すると、出雲の国譲りの舞台は現在の海陽町であったと考えられる。 続けて天孫降臨は国譲りの交渉成立後、アマテラスの孫ニニギが高天原から出雲へ降り立った話だ。 皇室儀式の深曾木(ふかそぎ)の儀では、右手に桧扇、左手に小松と山橘を持ち、青石を2個踏み「南」を向いて立ち、日置盤からぴょんと飛び降りる。日置盤を高天原と想定すると、右手の桧扇が神山町特産のヒオウギ花、左手の山橘も同町特産のスダチ、青石が阿波の緑泥石片岩を示唆しているのなら、神話の舞台は徳島県であったと考えられるはずだ。
ニニギが天下りを示した南方には、その後妻となったサクヤヒメを祀る室比売神社(阿津神社)やニニギを先導したサルタヒコを祀る御崎神社が海部川沿いに密集する。
天孫降臨条に「この地から韓国(からくに)に向かい(中略)…底津石根に太い柱を立て、空に聳える程に壮大な宮殿を建てて住みました」とあり、前段の大国主への国譲りの条件であった「底津石根に太い柱を立て、空に高々と聳える神殿を建てた」の言い回しと同様の内容がみられる。この大宮殿を示すのが海陽町那佐大宮で、往古より当地に鎮座していたのが和奈佐意富曽神社である。また海人の拠点である同地から韓国へと向かった事も暗示している。
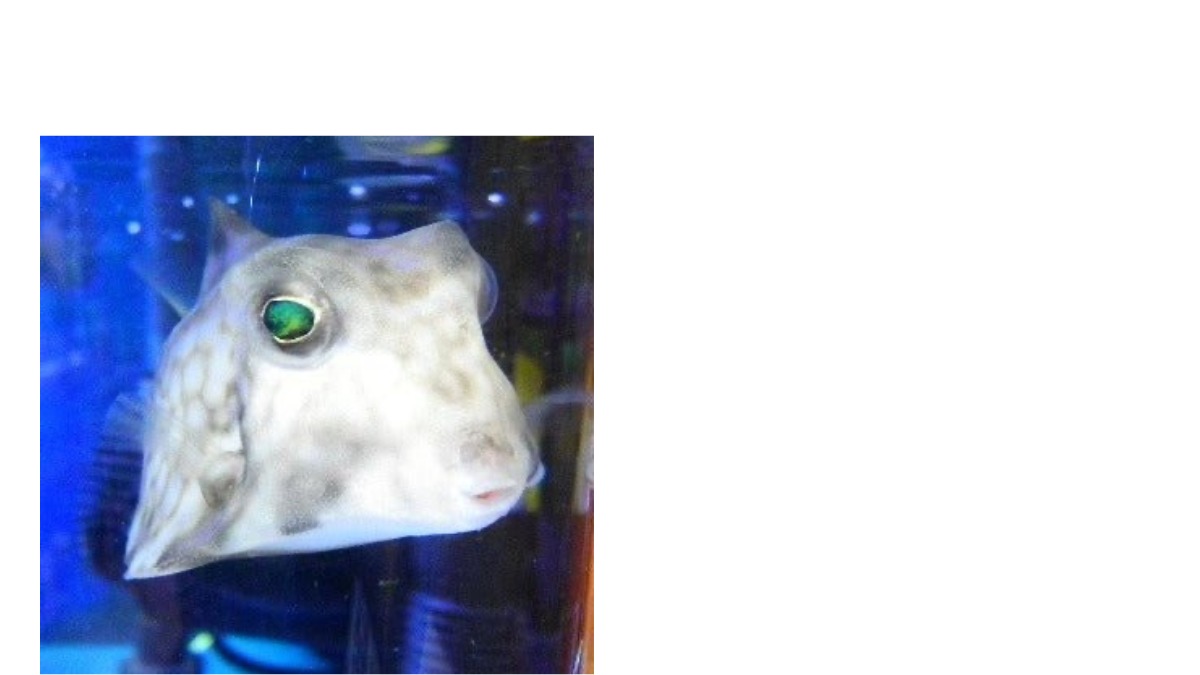
【執筆/コラク】 [問い合わせ先]なし |
コラク氏の説をもっと詳しく知りたい方は・・・
▶▶公式ブログ
ヤマモトタケルノミコト氏の説/天孫降臨と国譲り 阿波こそ神話を紐解く舞台
日本神話の中で最も輝きを放つ「天孫降臨」と「国譲り」。それはヤマトの国が誕生する瞬間を描いた壮大な叙事詩ですね。通説では、日向(宮崎県)に天孫降臨して、出雲(島根県)で国譲りされたと伝えられていますが・・・距離離れてますね。本当の舞台は四国・阿波にあった。全国に散らばった物語が一つに結びつきます。
まず、天孫降臨の前段として語られる伊弉諾尊の禊。『古事記』に「阿波岐原(あわぎはら)」と書かれてますね(笑) そう阿波であったんです。阿南市見能林町の海岸部であったんです。波間に輝く陽光から天照大神が、夜空の静けさから月読が、荒ぶる海風から素戔嗚が生まれた。まさに阿波は神々の聖誕地です。
やがて高天原を治めている天照大神は、孫である瓊瓊杵尊に「葦原中国を治めよ」と命じ、五伴緒神と降臨します。途中、猿田彦が道案内にきますね。これが天孫降臨です。そして随伴した天太玉命は、のちに阿波忌部氏の祖となり、天皇の祭祀を支える一族として歴史に連なっていきます。阿波は皇統と祭祀を結ぶ「聖なる始まりの地」だったのです。さらに壮大なのが「国譲り」。大国主命が治めていたイズモを、天津神の使者が譲れと何度も交渉に来たすえに大国主は国を天孫に託します。ここに天と地が一体になり、いや二つ以上の部族がひとつになり、和合して日本建国の正統性が確立されたと考えます。その地こそ阿波であり、残された伝承や社がその記憶を今も息づかせていますね。
はい、本題はそれが徳島のどこですかとの話ですね・・・。私が学んできた「天孫降臨から国譲り」の場所を順番に記載してみます。
①剣山神山山系から気延山国府
②高越山方面から穴吹美馬方面
③太龍寺から阿南の南方面
④眉山を中心に南の小松島阿南方面
⑤和奈佐意富曽神社で国譲り。
最も大事な場所ですが、多数の候補地がありますね。記紀のどの部分を最も大事な部分として採用するかでこれだけの候補があり本当にどれも聞いてみると面白いです。少し条件を並べてみると、大国主が治めるイズモであり豊葦原水穂國である。竺紫の日向の高千穂峰。韓国に向かう。笠紗の御崎に眞来通る。朝日の直刺す國、夕日の日照甚吉地。考えるほど・・。まずこの場所を確定させるために各先生方で一緒に何度も討論を繰り返して掘り下げて掘り下げて意見を纏めていきたいですね。はい、このままでは逃げてると言われますね。大変な浅学ですが直感で書きます(次回に考えが変わっていてもお許しください(笑))。私は剣山周辺から穴吹経由(磐境神明神社)で神山から気延山国府へ降臨。そして吉野川下流へ。やはりイメージでは聖なる剣山神山山系から吉野川下流へと天孫族が範囲を広げていったと考えます。
最後にまとめると、天孫が降り、地上の王が譲り、神と人とが一体となって始まった日本。そのすべての物語は、阿波の地を舞台に繰り広げられた。阿波は世界でも類を見ない国を譲って建国、和合した素晴らしい場所でまさに聖地と言えるのでは。この阿波から始まったヤマトの話を多くの方に知ってもらいたいですね(笑)。

▲天孫降臨。

【執筆/ヤマモトタケルノミコト】 [問い合わせ先]heartfull80@gmail.com |
ヤマモトタケルノミコト氏の説をもっと詳しく知りたい方は・・・
▶▶邪馬台国は阿波だった!(YouTube)
▶▶アワテラス歴史研究所アワラボ(Facebook)
▶▶一般財団法人阿波ヤマト財団(公式HP)
テーマ⑨【完】。
次回のテーマ⑩は・・・
「日本最古か!? 海陽町の多良古墳群」
記事公開日は2025年10月1日(水)。乞うご期待